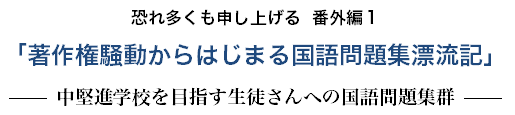 ■ 「四谷大塚の国語問題集」が使えない!
数年前、著作権のお取り調べが受験問題集業界にまで至り、それまで野放し状態だった著者の権利が尊重され、問題集改訂の嵐がやってきました。不思議なことに世間ではさっぱり取りざたされませんでしたが、おかげで突然、問題集に採用される文章が毎年大幅に差し替えられるようになりました。それまでも差し替えは出版する側の都合である程度はあったことでしたが……。
■ 国語担当講師が音を上げる!
この間、国語担当の困ったことといったらなかったです。途中入塾生などは、去年分の問題集の手配もままならず、しかたなく臨時にコピーして(この件きちんと四谷大塚の了解を得ました)対処せざるを得ず、そのこと自体もまた混乱を呼びました。つまるところ教材管理上、大げさに言うと何が何だかわからない状態に至りました。
■ 国語の問題集は読解力のために
英語を習うとき、「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能を分類します。このうち、私立中学受験の国語教育は明治以来、「聞く」「話す」は限りなくゼロに近い。「書く」は補助手段。漢字系・語句系のみ、まあ「書く」にも分類される部分がありますが、今に至るも結局「読む」に特化しています。 国語の問題集が必要な理由は明快当然です。第1、かつ主要な理由と言えば、「まともな文系学力は読解力で判断される」からです。そうと決めたら、「少年少女なりの読書人」であればいいのです。近頃「速読」がはやり、中学校によっては速読で1000冊読破などと言い出す学校がありますが、1000冊志向はどうも私はなじめません。本は「吸い込まれるように読む」ものでしょう。
■ 読書離れの現実を前に
ところが、今日の潮が引くような読書離れの現実の前に人工的に国語読解問題集から「読書≒読む技能」の習得を始めざるをえないのです(「≒」についての異論は百も承知の上です。異論ではなく大局的にはおそらく正論です。日本にはこれ以外のタイプの国語修練本は実質ないのですから仕方ない。)。本当は本を読む少年少女を増やす、またはそういう環境をさらに作るべきなのですが。いくら本を薦めても、まさか読書の自習でお金はいただけない。塾も予備校も保護者にお金を請求するには授業時間内では問題集を使わないわけにはいかないのです!
■ 「読解力を数字で表す」入試
それに加えて何と言っても入試の形式だからです。文章をまず読ませて次に読解力を見る。そのために後ろに本文についての設問が付く。これしか100年以上に渡り洗練されてきた「読解力を数字で表す」方法がないからです。私どもでもそうです。ですから、「吸い込まれるように本を読む」体験で「読む」力を得る以外の方法としての国語問題集利用とあいなるのです。うーん、何かないかねー他の方法……。 実は私立中受験を論じるからこうなるだけで、公立中高一貫中受験の文化が大部固まってきましたのでそろそろ言える時期になってきました。つまり、作文を学力として見る土壌が出来てきたのです。ただしそれはまた別の機会にしましょう。
■ ついに「四谷大塚国語問題集」使用から離脱を決意
算数・理科・社会は表現の仕方から写真や図表は別にして著作権チェックがはるかに緩く、この著作権の取り調べ大改訂からは逃れられるため、目に見える現象はほとんどありませんでした。それだけに、この「国語問題集の出題文改訂」の嵐には参り、ついに四谷の4科セットを購入することをあきらめ、国語だけ教材を分離することに決めました。
もう一つの理由は、下町の生徒さんは後に言及するように四谷のテキストとレベルが乖離しすぎている子がけっこう多く、そもそもテキストの世界に入っていけない子が多いことです。テキスト自体が悪いわけではないのです。
■ 離脱は小さな塾だからこそ
それにしても普通のYT塾さんではこういう「想定外離脱」はできません。週例テストに縛られるからです。塾が小さいためにできたことで「〜の巧名」でした。4科セット使用は長いこと当然と思っていたことでしたので、決めるまでに気持ちの整理が必要でした。そういう変則購入を許していただいた四谷大塚さんにも感謝!
書いている私は国語の専門家ではありません。国語の試験問題はずいぶん見ましたが、東京都は私立中がおおむね100校あるのです。全部の傾向性を把握するのはしょせん無理です。最もそんなことを言い出すと専門家と言える人はほんの一握りしかいません。ですから、この職業に30年携わっている準専門家というぐらいのことにして、一応私なりの考えを書きます。生兵法へのご批判は覚悟しています。
■ 1冊目として入門用「コア問題集国語」を採用
コア問題集を採用した理由は簡単です。出題文が教科書準拠だということと、設問形式がくどかったからです。当方がお預かりするお子さんの中には、しばしば国語のセンスが「ない」ことを「自慢にする」ほどの方がおられます。下町特有の反ディレッタンティズムです。あきれるような事例に事欠きません。加えて今の時代の活字離れです。まったくもっていけません。
■ 「コア」の「くどさ」は貴重
コアは同じ文章が2度採り上げられ、2度目は同じ文章に対して違う設問を投げかけます。このくどさは初心者には貴重です。加えて15ページ見当ごとにチェックテストがあります。実はこのチェックテストが大正解でした。初心者のお子さんはただ「進める」だけです。見直しなどという習慣は国語科目ではまずありません。もちろん漢字だけは独立して存在し、見直しもありますが、本文の中ではしないことです。もっともチェックテスト自体にもある「長文問題」がこれまた本文とは別仕立てで、わからない子はまたわからない。ですが、これはもう仕方ないことです。このように「文が長くなく、くどく、細かく」設定してあるのが初心者にはいいのです。あくまでも初心者に、です。
■ 国語教師はどう対応するか
教師がどう対応するかですが、一方的に解説し、解答しても私どもは無駄と思っております(ちょっといいすぎかもしれません。ベテラン国語教師という独立弧峰の存在が可能ですが、東京都内の塾にどれだけおられるか……おそらく上限100人いるかなー……圧倒的に足りません……)。あるいは自学自習できる国語学力上位者のみを対象にしている大手塾の上級クラス生なら可能です。当方がお預かりしている生徒さんである、学力中位生でも、大人の手助けがいります。いわんや先ほどの反ディレッタンティズム生は……です。
要するに教科書以外の文に接したことがないのですから。長い文に接していると嫌になってくる。彼ら風に言うと「頭がボワーンとしてしまう」のです。論説文など何を言っているのやら、ごっちゃごちゃなのです。近頃大解剖されている脳の構造説明風にいうなら「脳が必死の努力で未体験なことをしている」のです……エッ、もういい? わかってくれました?
■ 集団授業がすべてではない
とにかく、ほうっておいたら、彼ら・彼女らはこの種の論説文など自主的には一生読まないのです。一生です!(「わかったようなことを言うなよ」とのお叱りは覚悟しますが、まずそんなところです。)スタートがこれですから、国語を教室で一方的に解説解答する授業は厳しすぎます。それでも大手さんではしています。理由をある本(※)が解説していますが、その通り。経費節約からです。どの科目も先生一人で教壇から声を張り上げるという一律なことがまかり通ること自体、そもそもおかしいのです。算数系はかなりのところまで先生一人授業は可能ですが、国語系は少人数でないと無理だと思います(英語も同じでしょう)。
■ 究極の方式、ベテラン2人の個別指導
この前提にたって私どもは方式を変えました。個別指導です。具体的にいいますと、一挙手一投足全部教師が見ます。一人一人間違いを指摘し、正しく直させ、○を付け、二度目は色替えの○を付け、はんこを押し、小テストをさせる。要するに、考えつく小技を全部駆使する。悲しくなるほど愚直に、です。
個別指導塾の不慣れな先生が不慣れ故にそうせざるをえないことと、表面的には同じ事をするのです。ただし、水面下の作業量はまったく違います。一例を言いますと、一授業で同時進行する教材が少なくても3種、約500ページ、ひどいときは5種800ページです。事前チェックだけでも、時間と手間が相当かかります。実際、私はこの準備作業に今年は余暇を明け渡して半年かけました(1)。ですから、これではどんなベテランが見てもせいぜい4人〜5人です。他塾方式なら20人〜30人を一人で教えきるスター教師レベルのベテラン2人で作業しているのです(一人は指導歴30年以上、もう一人は早稲田大学を始めとする文系大学の非常勤講師。それも5大学で講座を持っている第一級・本物の学者!)。うーん、我ながら何とも贅沢なことです。私が親か生徒なら「こんな機会はまたとない」と即入塾しますね。
■ 「やりっぱなし」の個別指導塾に注意!
ついでに申しますと、個別、もしくは個別に近い形態をとる塾の国語は、大方「やりっぱなし」です。○付けも、ひどいと先生自身が生徒の問題集に模範解答を丸写しして終わり。もっとひどいと穴だらけで進んだことにしてしまうやり方(?)です。転塾してきた生徒さんの問題集・ノートで何十例と見てきました。親御さんはこの惨状をご存じないのでしょうか……。どうも塾の連絡帳を過大に評価なさっておられるようです。確かに、個別指導の安心材料は「連絡帳」ですが、連絡帳は真実ではありません。お子さんの問題集・ノートをチェックしてみてください。
■ 「コア」は出発点にすぎない
冷静に見ると、「コア」は教科書から引っ張った例文で出来ています。やはり到達目標はあまり高くはありません。もっとも、逆に考えると、それが日本の平均値です。中学入試はその平均値を大幅に上回る作業です。ですから四谷大塚のテキストを見慣れている方からすると、「コア」は「簡単すぎる」と言われます。その通り、私どものやり方でも、この本はただの出発点です。進む生徒さんはどんどん進みます。週2日、毎1時間の授業シフトのなか、2ヶ月で1冊進んだりします。遅い生徒さんはもちろん自分のペース(率直に言いますと4ヶ月)でしっかり理解していきます。誰一人空回りしません。
■ 2冊目として「ウインパス問題集国語」にリレー
終了した生徒さんから順に2冊目、3冊目とコアに続く問題集に進ませます。初年度は「ウイニングA・B」を採用しました。これは実質、「ウイニングA」が5年用、「ウイニングB」が6年用です。「ウイニング」は標準的な受験を意識した問題集で、悪くはありません。
ただし、1)必須小道具のチェックテストがないこと、2)「語句のページ」の部分が塊として長すぎる(一度に20ページ余りもある)こと、3)一つ一つの文のレベルは「コア」を越えるが、判型がB5版のため、出題スペースに余裕がなく、その結果として記述式がやや少なく、選択肢問題が多いこと、この三つの理由から、2冊目タイプではないと判断。最初の1年の試行錯誤の後、このシリーズは予備の3冊目に回し、2冊目問題集として「ウインパス国語シリーズ」(文理)を採用することに変更しました。(2011年3月で「ウイニング国語」はやはり廃版になりました。)
■ 「ウインパス」は図書室センス
「ウインパス国語」は「コア」と比べて記述式が倍以上。選ばれている文章のセンスが悪くない。例えて言うなら、「コア」は題材が教科書センス、「ウインパス」は図書室センス。ただし、下調べの結果、物語の出典がほぼすべて「最近の女性作家」なのです。当方成年男子のため、文章からたちあがる「妙なぬらぬら感」とでも言えばいいのか、「気持ち悪さ」に実は若干辟易しました。当方、自分で言うのも何ですが、かつて子供の本にセミプロ級まで凝ったことがあるのですが、その結果おそろしいほどの偏向した意見にたどり着いてしまった経験があります。「日本の児童書ってやつは……だめだ!」という立場です。一刀両断は私の悪い癖で、真実はもう少し手前にあるのはわかっているつもりなのですが。ですがねー……。20年前の話です。当時「よし、合格」と行って膝をたたいたのは、岡田淳のたいがいの作品と、佐藤さとるコロボックルシリーズぐらいでしたか……なつかしい赤城かんこさんの「本の探偵」がブームだったころです。赤城さん、今どうしているんでしょうか……。
■ やや女の子向けに偏り
話を戻します。つまり、潜在的なかっこよさを持っている(つまり後一歩の)男子とその子を応援している女子みたいな文が多すぎませんか? かっこよい可能性を秘めているのだが、もう一歩どこかずっこけている、結局「女子から見たかわいい男子」だな。漫画みたいだ。一方、主人公が女子の場合は、かなりの確率で「心理戦記」だ。教室の中の毎日の闘い……。読んでいて「がっかり悲しく(こんな言葉ないですね)」て泣きたくなる。「何かないのか? 突き抜けた話は!」。また極論になってしまいました。とにかく西原理恵子が大人に受ける理由がわかります。問題集に心の解放区を要求してはいけないのでした(2)。
というわけで、そこが困る点だったのですが、ウインパスは2冊目としてなかなかいいのです。今年度採用! 目下5年生で大活躍中です。
中間報告:予想より生徒達、すらすらと解き、どんどん進む。あれ? どうしてか……漢字・知識タイプが別冊なせいか……。
■ 3冊目は入試対応問題集「実力錬成問題集国語」
「ウインパス」はとてもいいのですが、まだ中学受験完全対応ではないのです。一番わかりやすい例を述べるなら、出題文に「〜中学」という出題校メモがないのです。この点、「ウイニング」は一応あるのですね。しかし、先に述べた理由から、3冊目は「ウイニング」ではなく、「実力錬成問題集国語」(文理)を採用しました。出題文に「〜中学」という出題校メモがあり、さらに版形が見開きA3で一覧性があるので見やすい。問題文の選択眼もいいのです。
これでようやく私立中学入試問題集のレベルにたどり着きます。ここまで実は6冊。さらにいうなら副読本の「漢字ガイダンス」と「ことばの達人」をあわせて計9冊。やり終わった本を本棚に並べるとなかなか壮観です。
■ 進度が早い生徒は10カ月で6冊
この6冊を仕上げるのに、早い生徒さんは小4年の2月から始めて小5年の12月中ごろにたどり着きます。そういう進度が速い生徒には控えにしておいた「ウイニング国語A」も渡し、小6にさしかかる2月〜3月ごろ、一つ上の小6版コア・ウインパス・錬成・ウイニングB・サーパスと進みます。そして最後は各私立中の過去問ですね。
■ 国語教師の下調べ作業は必須
この経過を経て、一番いいたかったのは、実は下調べ作業です。生徒一人一人に合わせますと、毎回のこちらの守備範囲が膨大なものになります。個別指導塾の新米先生ではここがネックになります。つまり、そこそこの問題を生徒一人一人の範囲にあわせて説明しきる守備範囲能力です。私の場合も、国語を担当する際に心理的におっくうになる理由はそこです。文章の細部は驚くほど忘れています。2ヶ月もするとメモを見ないと受け答えがスムーズでなくなります。受験クラスでない総合クラスと称している週2日対応のクラスでも、この問題集は導入しています。先日など1クラスで5人の生徒さんを預かった際、学年も問題集もばらばらになり、5冊を同時並行で見ることになりました。さすがにこちらも脳みその整理・切り替えが辛かったです。突然こういう授業の対応を迫られたら私もできません。下調べがあっての賜(たまもの)です(3)。
■ 難関校の問題をどうするか
万が一お読み下さっている方からの疑問その1だと思います。要するに難関校は全存在をかけて長文を出してきます。生半可な対処でできるものではない文章です。長文速読力と、「説明しなさい」という解答の仕方、つまり本文にない言葉も含めてまとめあげる能力、さらに、文の背後に潜む気持ちの忖度(そんたく)まで要求する。小学生の実年齢を越えた精神年齢を要求してきます。もはや大人でもしんどい領域です。何を隠そう、私自身、本当は解きたくありません。仕事ですから解きますが。良い文章なのですが、実際にする作業は「『読む』という楽しい作業とはまったく別な、したくもないしんどい作業」ですから、解き始めるのに気持ちを奮い立たせなくてはなりません(4)。
■ 最後に過去問へ
虚心に臨めば、どの中学の問題も得難い良い問題です。「受ける学校ではないのでしたくない」という狭い心は禁物です。国語嫌いの方ほどこの傾向があります。国語領域の中の「読書」に重なる部分が出題文には必ずあるのですから、例えば、教えているこの私にしてからが、出題文の大半については「へー、そうなんだ」という知的興味がわくのです。これがない生徒さんはつらい。要するに、この段階まで来ると、もはや「教養」という領域での勝負なのです。反ディレッタンティズムそのものが障害です。ここらは「家庭の力」と言ってしまいたくなるのですが、まあ、こちらサイドにしぼって言えば、「指導者の力量」ですかねー……。うまく誘導して下さる良い先生だといいですね。
当塾はここまでします! 以上、漂流の結果報告です。
■ 脚注
(1)講師の先生の中には下読みしないで説明できると豪語されるすばらしい方がいましたが、その能力は特殊かと存じます。私にはできないのです。読んでもいない設問をとっさに解答したり説明したりなど、冷や汗しか出ません。無理なことは無理なことです。下読みしていても、少し間が空くと解答の根拠を忘れてしまいます。さらにひどいときは文の内容まで忘れています。特にひどいのが段落分け問題で、とっさにはまず分類の根拠が浮かびません。無心でほぼ全文を読み、ようやく「そうか」とわかります。実は、私は未だに段落を分類して解答する問題は大嫌いです。わからない子に短時間では説明できないのです(相手が全文をまだ把握していないのですから……)。接続詞を利用して説明するタイプの方がいますが、それはテクニックですよね。本当は、全文を脳の中でプールして、鳥瞰図のように見て、部分分けして初めて意味があるはずではないでしょうか。それは年端の行かない子供にはどうなのでしょう。このタイプの設問そのものが、本質的に無意味な気がするのです。段落分けは、自分が「書く立場になったとき」に初めて必要になるのではないか、それまでは、つまり小学生まではいらないだろう(おそらく高校生以降からでしょう)というのが私の個人的な見解です。
(2)その割に現場は熱くありません。はっきり申します。受験問題集の書評がありません。首都圏の2〜3割の子供がここに関わっているのです。しかも問題集なのです。下手をすると教科書以外これしか接しないまま大人になっていくのです。その問題集業界にまともな書評メディアがないのですから……。現に、私が手探りのままこんなものを書いてしまう始末です。かつてなかったのは致し方ないのですが、このインターネット時代です。誰かが言い出せばこの業界、実は優秀な先生が本当に多いのです。しょせん問題集だからと過小評価せず、生徒のためにも書評めいた運動がネット上ならできるはずですよね。
(3)いやー、私としてはよく読みました。何しろ多感な年頃の少年少女を預かる立場です。我に返ると空恐ろしいほどの責任がかかっているのを肩に感じます。予備の小4コア・ウインパス・実力錬成も含め、計12冊分の脳内ストックです。一時期、頭がパンパンにふくれました。
(4)「サーパス」問題集は開成中学の問題はありませんが、麻布・武蔵・双葉・慶応・筑波大付属・灘・駒場東邦・ラサールなど、ほぼ首都圏・関西圏の名だたる名門校の問題が載っています。ですから、記述式が多く、厳しい内容です。普通の小学生には端から無理です。中学生でも同じ。大人でも、仕事でなければしたくないことです。
(初稿:2010年7月25日 最終稿:2011年11月6日)
|