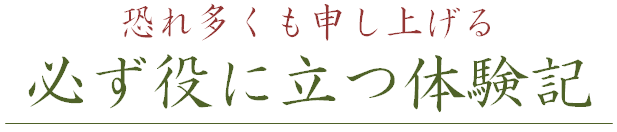| ☆☆☆☆☆ | All Creatures Small And Large | James Herriot (1972) |
| イギリス、エセックス郊外の若き獣医の記す心温まる小さなエピソードの数々。どの掌編でも彼は自己を主張せず、相手の行動で語らせる。邦訳が「ヘリオット先生奮戦記」。うまい!彼を雇った獣医ジークフリードとその弟の日々のエピソードが強力にからむ。ヘレンとのなれそめから結婚までの失敗話がまたいい。イギリス高地の農村の日常風景がいい。 全編楽しめます。 |
| ☆☆☆☆☆☆ | Da VINCI CODE | Dan Brown (2003) |
| いやーうまく作った!活躍する場所、歴史、謎解き、どれ一つとっても一級。 |
| ☆☆☆☆☆☆ | A Matter of Honour | Jeffrey Archer (1986) |
| 冷戦下の話。少し古いのですが、「イーコン」をめぐるこのジェットコースターのようなストーリー展開はすばらしい。本を置くのが惜しい心境になります。鉄板としてお薦め。 |
| ☆☆☆☆☆☆ | Gone South | Robert R.McCammon (1992) |
| マッキャモンの典型作。奇抜な登場人物、思いもよらない話の展開。アメリカの南に、どんなオカルト的な桃源郷があるというのか、それだけでも興味が続きます。 |
| ☆☆☆☆☆ | The No’1 Ladies Detective Agency シリーズ(1) | |
| この英語の易しさで、10作を越える分量、しかもあきません。ボツアナの女探偵とその周辺の人々のエピソード、人は万国共通だと思わせてくれる点が最高です。余談ですが、見習いの若い方の名、9作目でわかります。お楽しみに! 現在PBで10冊発行中。まだ継続中。 |
| ☆☆☆☆☆ | Frost シリーズ(2) | |
| フロスト警部シリーズです。イギリスの仮想都市デントンを舞台にしたえげつない犯罪に昼夜なく、寝食も無視して挑むワーカーホリックの初老のおっさん警視(けっこう偉い?)フロストの物語。これが笑える、そしてイギリスの病理(というより現代の都市の病理)に鋭角でせまっているのです。ただし、緻密な推理に期待してはいけません。解決の糸口は案外・・・・です。署長マレットの、役人としてのあらゆるいやみ・小言・圧力をすべてスルーし、有能・無能な部下を引きずり回す消耗戦が特にお薦め! 作者他界のため全6冊。(最近別な著者で「若き日のフロスト」の話が出ました。未読) |
| ☆☆☆☆☆☆ | The Eagle Has Landed | Jack Higgins (1975) |
| 男性しかおもしろくないかもしれません・・・戦記物です。第二次大戦時のドイツ兵の一部隊がイギリスに潜入し、チャーチル殺害という目標にせまるのです。そんな無理なこと・・・ところが予想に反して・・・、しかも人の心の琴線に触れる出会いまでありなのです! |
| ☆☆☆☆☆ | Pied Piper | Nevil Shute (1942) |
| 初老の紳士がなぜか第二次世界大戦勃発時のフランスを他人の子を何人も預かりながら縦断し、イギリスに逃げるというちょっとありえない設定の話です。ありえないにもかかわらず徒手空拳、ぞろぞろと子供を従え、この難事を達成してしまうのです。 |
| ☆☆☆☆☆ | The Main | Trevanian (1976) |
| カナダのモントリオール。知名度とは違い、どうやら寂れた町。そのメイン地区を担当する刑事LaPointe、愛する町を徹底的にどんなことをしても守り上げる。やがて上司による移動の強要。がんとして拒む主人公。その彼のところに娼婦の娘が偶然のようにして同居する。親子のような、恋人のような、不思議な関係。愛する妻に先立たれた主人公の寂寥に小さな明かり。それも長くは続かない。しかもややこしい話がからんでくる・・・事件は解決するが、寂れた町の誰もいないアパートに帰るだけの刑事LaPointe・・・・思わず「よし、それでいいんだ!」と叫んでしまう刑事小説! |
| ☆☆☆☆☆ | Adventure Capitalist | Jim Rogers (2003) |
| 最後は明日を切り開くヒントとしてこの本とします。世界各地をベンツで許嫁と旅する記録です。日本編もあるのです。おそらくここに登場する日本が今思えば技術立国としてのピークだったのかもしれません。現在の中国・韓国の台頭を思えば・・・このジャンルに精通しておられる方からすると「古いよー」でしょうが、当方は断言します。ジム・ロジャーズはぶれません。一貫しています。ですから古いのは当方ですので「最新作目指して今後もがんばります」と一言申してこの洋書(英書)推薦という暴挙を一旦閉じさせていただきます。 |
 鉄板の児童書 10冊
鉄板の児童書 10冊 単語制限本 5冊
単語制限本 5冊 ジューベナイル(10代向け)10冊
ジューベナイル(10代向け)10冊 一般向け 10点(25冊)
一般向け 10点(25冊)