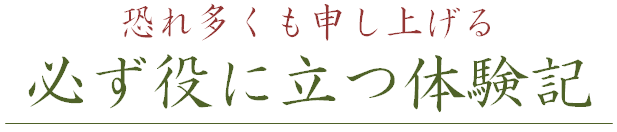|
英検準1級合格体験記
〈前編 英検準1級への道 1〉
 英検準1級考 英検準1級考準1級はどの検定においても「アマチュアが到達できる限度。ここから先は各自、好き勝手に!」と思うのが一番建設的なこの級の位置づけかと思います。
そして、英検準1級はもちろんそれなりにしっかりした資格です。ところが長期的にTOEICにおされて受験者数そのものがこの10年で二分の一以下に減じました(1)。少し前に合格した者としてエールを送る意味もこめて(?)準1級シリーズ第2弾を載せます。たいした実力でもないのに、話が大仰、かつ細部にこだわり過ぎるのは、そういうタイプの奴だと今回も笑ってお許し下さい。
2007年現在の文科省発表で、中学の英語の先生の4人に1人、高校の英語の先生の2人に1人しか英検準1級以上を取得しておられないそうです。その2年前に始まった教員への物心両面のてこ入れの結果ですから、英語を職業としている人でも未達成者がかくもたくさんいるのです。一方でプロと自称できるのはどう間違えても英検1級以上、TOEIC900点以上です。この中・高の先生レベルと、プロのレベルの中間の資格が英検準1級です。悪く言えば中途半端です。
しかしながら英語を「趣味」もしくは「職業としていない」私からすると、ある程度集中しなければ英語に習熟できないのだし、勉強のようにするのも本末転倒なので、資格挑戦はどこかで切り上げなければなりません。その視点からすると切り上げ時を決めるのに本当にいい資格でした。
 英検3級からスタート 英検3級からスタート英語は中年になってからやり直した典型です(1)。ひょんなきっかけから英検は3級→準2級→2級→準1級と初めから全部受けました(2) (3)。公開試験会場の某中学校は春はうぐいすが「ホーホケキョ」と鳴くのんびりした所。英検3級から始めたせいで、さすがに笑えるエピソードが多かったです。
3級の2次面接試験のときは会場ですれ違う中学生という中学生が私を試験官と間違え、挨拶してくれました。頭のはげた受験生など3級にいるわけないですものね。試験官は中学生への対応にやや厭きていたらしく、毛色の変わった奴が来たと、とりわけフレンドリーでした。しかし、初めから最後まで、恥ずかしかったー・・・
 英検2級の面接にて 英検2級の面接にて2級では二次の面接試験、順番がほぼ最後で、控え室には分厚い英英辞典を繰っている大学生風や、どうみても中学生の女の子など一風変わった子が散見され、気圧されました。その結果かどうか、いやーあがりました。まあ、英会話には縁がないままの生活だから初級会話を超し始めるとしどろもどろにそりゃーなります。それに試験会場が狭い応接室ときました。試験官との距離が異様に近すぎました。試験官がつけている成績欄が何点かわかってしまうのです。答えが試験官に受けると、つけかけていた手が一瞬止まり一つ上に○されたりするのがそのままわかるのです(一つ下だろうですって?)。
準1級を初めて受けたときは、最初の単語試験の4択問題で4つとも全部知らない設問があって苦笑いしました。手の施しようがないとはこのことでした。もちろんこれでは不合格でした。それでも不合格Aだったことが本当にうれしかったことを今でも覚えています。落ちて喜んでいては世話ないですが、Aは「また出直しておいで」という合図に感じたのです。
受かるための対策を簡単に分析すると、単語は英字新聞タイプと判断。これは訓練しなければだめと覚悟し、意識的に英単語練習をしました。並行して英字新聞対策。さらに英語の文章に慣れるため、高1英語教科書音読。その他散歩の折の音聴毎日1時間。そして1つだけ過去問対策集を最後に集中して2週間。もともと「問題集による英語の勉強はしたくない」と鹿野晴夫さんをみならって意地を張ったため、問題集勉強はこの本のみでした。
 英検準1級へ 英検準1級へ英検準1級の一次試験の成績
英検準1級の二次試験の成績
英検3級受験から準1級合格まで、歩みはのろかったですが、目標が明確だった分、充実した2年半でした。
 英単語で全滅! 英単語で全滅!前述の通り、7500語(英検発表)の壁は当初ただならないものでした。私は鹿野晴夫さんの本に刺激されて、DUO2(1997)の音読を基本として単語増強をしていました。おそらく50回前後の音読をしたと思います。その延長上で英検準1級を初めて受けた日にもDUO2のナチュラルスピード版のCDを初めて聞きながら会場に行った記憶があります。ぎりぎりまで粘って1題でもこの中から出ないかと祈っていました。結果は無惨。DUOでは決定的に単語量が不足と判断し、他に2冊「TOEIC 必修単語2700(1996)」「WORD MAX (1999)」を利用しました(1)。英検発行の「英検Pass単熟語準1級」も購入しましたが、この手の単語だけ並べてあるタイプは私には無理で利用しませんでした。例文方式にすれば喜んで利用したのに、もったいないです。
そして準1級用としての反省から旺文社が高校生用に英字新聞として編集した、「蛍雪Junior Times 1.2(佐久間 治編)」をとにかく音読しました。この本は本当によい本でしたが、残念、この2冊で後が続きませんでした。実はそこに出ていた単語が私には大いに役立ちました。それ以上に新聞の英語にずいぶん慣れました。トピックスの内容といい、いい本だったのですがねー。ついでですが、大人用の新聞ダイジェスト本は政治欄が多すぎませんか。私、相当堅いたちですが、その私でも正直厭きます。
 中学の教科書 中学の教科書長文については神田の三省堂に行き、教科書発売コーナーで当時日本で発行されていた中3の教科書全7冊を全部購入し、確認しました。いや、中3用と馬鹿にできません。本当によくできています。そのうちの1冊「Everyday English 」を選び10回ずつ音読することから始めました。このテキストはおもしろかったです。例えば、ラナルド・マグドナルドってご存じですか?(マックじゃないってば!)
 高校1年生の教科書 単語制限本の雑誌タイプなのです 高校1年生の教科書 単語制限本の雑誌タイプなのですその後高校1年生用英語教科書を14冊(1)、すべて10回づつ音読しました。だいたい一冊80〜90ページで計約一万ページ読んだことになります。音読は勉強ではなく訓練です。ですから毎日の習慣にさえできればつらくないです。
それに、この高校1年生用英語教科書は本当に楽しくできています。入手が各都府県一店のみ販売とやや困難なためご存じない方も多いようですが、その気にさえなれば音源も併用できますし(2)、良質の雑誌を1冊見ている気がします。ついでですが、これが高2用教科書になるととたんにおもしろくなくなるのが不思議でした。実は私は社会人にこそ、この英語の勉強をお勧めしたいと思っています。教科書と思うからつまらないので、雑誌と思えばいいのです。てごろな値段の雑誌がこんなにあるのです!使わない手はない。キャッチフレーズ風に言えば高校一年生用の英語教科書は「単語制限本の雑誌タイプ」です。
 英字新聞 英字新聞
駅売りの新聞をずいぶん見た時期があります。おもしろかったのですが長続きしません。どうしても部分しか見ないことからくる未達成感がつきまといます。そこで、前述の2冊の「蛍雪Junior Times 1.2」をひたすら音読しました。これだと英字新聞を読みきった満足感がありました。それに内容につられて単語や表現をよく覚えましたし、ラペンタさんのファンにもなりました。
 気がついたら音読・音聴三昧 気がついたら音読・音聴三昧かっこに答えを埋めたり選択枝から選んだりする学習方式が苦手なことと、字が雑なため紙に書く勉強を避けました。結果気がつくと声を出して本を読む、音源があるものは利用して聞く。利用したどのテキストもそのタイプばかりでした。旺文社の「7日間完成英検予想問題ドリル」、これを3回目の検定の直前に2週間毎日しました。問題なれにはとてもよかったです。
(c) 2004-2014 必ず役に立つ体験記
|