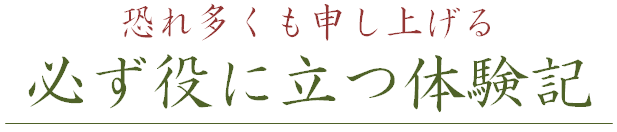|
数検準1級合格体験記
〈後編〉
 さあ、テストです さあ、テストです準1級、1回目の受験は2級のときと同様、計算のみの挑戦に等しく、偵察。それでも何題かチャレンジし、それなりに時間一杯考えました。その意味では普段しない、推理の頭をつかった爽快感がありました。
テスト終わってもリズムを崩さず、次の2回目に備えてまたひたすら教科書の学習をしました。家人から白い目で見られ続けたものです。当人はこの時期、乗りにのっていました。たぶん人生の中で数学やっていて一番楽しかった気がするほどです(エー本当かよ~!と言いました?ネットを通して聞こえる気がしますが・・・本当ですよ・・・)。
 数検準1級 第92回 数検準1級 第92回そして2回目、1次で思いもしなかった問題選択の迷いが生じ、めんどうな展開がからむ「ねじ伏せ問題」にてこずり、今回は危険な結果になってしまいました。申し込みのときに実は迷ったのですが、免除申請をあえてしなかったのです。本当は受けなくてもいい1次だったのでした。後でおわかりのような次第ですので、5000円と時間がもったいないのでこういう馬鹿なことは皆さんしないようにしましょう!
2次、問題との相性が合えば奇蹟もあるかもなー・・・ぐらいのスタンスでしたが、 第1問〔選択〕は有名なヘロンの公式の四角形に適用する問題。やったーこれはできる。
第2問〔選択〕「(logx)の二次方程式〔省略〕を満たす2つの実数xが存在して、それらがすべて1より大きくなるようなaの値の範囲をすべて求めなさい。」という対数の方程式、これも何とか・・・。後2問必須だから解くしかない・・・
6番〔必須〕の不等式・・・
x, y, zをx≧1, y≧7, z≧5を満たす整数とするとき、次の方程式の解〔x, y, z〕をすべて求めなさい。 3xy+4xz-xyz=5x この不等式、手こずりました。簡単だと思ったら場合わけが面倒で、あれこれ考えてもうまい狭め方が思いつかず、腕力方式でとりかかり・・・・ぎりぎり解答1つだけ見つけ、もう残り時間とのかねあいで無理と判断。
7番〔必須〕・・・f(x) = 2-a∫〔0からx〕{f(t)-b}dt を満たす関数 f(x) について、次の問いに答えなさい。ただしa, bは定数とします。
(1)g(x)=e〔指数としてax〕{f(x)-b}とするとき、g(x)は定数となることを示しなさい。またその一定の値をbを用いて表しなさい。 (2)f(x)を求めなさい。 何か難しい・・・
格闘した爽快感は思い切りあったのですが、完成答案1題。対数たぶんOK、不等式ひょっとしたら部分点?積分だめ。うーん・・・これはだめだ・・・また次回がんばれ!こんな感じでした。
そしてしばらくして結果が戻りましたら一次不合格、二次何と満点4点のところ2.5点で合格しているではありませんか。びっくりしたのもいいところでした。とたんに次回へのやる気がすーっと引いていったのを覚えています。
 もう一度やりました もう一度やりましたとはいえ完全合格ではないのですから、その次の回に2次を免除申請した上で3度目の一次受験をしました。2週間前ぐらいからノートを見直し、計算問題だけですから抜かりなくチェックし、7点満点で6点で合格、ようやく長ーい数検チャレンジを一端終了としました。
 数検 受験経過 数検 受験経過
( )内100点換算点
こんなしょぼいクリアーの仕方で申し訳ありません。若い方で理系志望の方は現在の高校学習をしっかりなさればいいのです。現状は数検自体が発展途上のため難関国立・私大理系の志望の生徒さんは受けもしないようですが、大学入学後は意外に忙しく、受験機会を失いがちです。受けるなら受験時代・高3時代の通行手形と思って受けられるといいかもしれません。
英検・漢検と違って数検は2008年現在、準1級までが最寄りの学校・予備校・塾で受けられる点が何と言っても利点です。遠くの公開会場にわざわざ行かないで済みます。私もそのおかげで気楽に何度も受けられました。こういうテストの常ですが、すでに私の様な数Ⅲ以外で得点を稼ぐのは無理になったのがいい例です。認知度が上がるといろいろと制度が厳しくなりがちです。
今回もおじさんの再チャレンジの話になってしまいました。これではエールになっていないと思いますが、皆さん、やればいつかは受かります。あきらめず是非チャレンジし続けて下さい!
 利用した参考書・問題集 利用した参考書・問題集 ブルーバックス CDROM「パソコンらくらく高校数学微分・積分 〔友部勝久・堀部和経 共著 2003〕 ブルーバックス CDROM「パソコンらくらく高校数学微分・積分 〔友部勝久・堀部和経 共著 2003〕グレープスソフトがとにかくお薦め。 同書79ページの sin xy = x+y のグラフ例などを出してみると、すごいですよ!その割に認知度が上がっていない気がします。がんばれ!グレープス!おじさん、応援してるよ!
 啓林館の教科書 Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ、C 啓林館の教科書 Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ、C数研出版の教科書も持っていますがややくどいので利用しませんでした。教科書のありがたみをこれほど感じたことはないかもしれません。徹底的に見ました。
 教科書レーダー Ⅱ、B、Ⅲ、C 新興出版 教科書レーダー Ⅱ、B、Ⅲ、C 新興出版自学自習者の友。答えがあるからこその存在。昔からあり、決して安くはない。これに付加価値を付けられないかなーと使ってみて思いました。例えば前述のグレープスで出したグラフを載せたりしたらいいと思いませんか。
 マセマの「元気が出る数学」シリーズ (シリーズ中一番やさしいタイプ)Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ、C マセマ出版社 マセマの「元気が出る数学」シリーズ (シリーズ中一番やさしいタイプ)Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ、C マセマ出版社公式の暗記の仕方など、すぐ使えます。自学自習者は見栄を張らない(そんなの誰でも当たり前ですか・・・)のが一番とつくづく思いました。
 数検協会発行の過去問題集 数検2級 旧版・新版 数検協会発行の過去問題集 数検2級 旧版・新版 数検協会発行の過去問題集 数検準1級 旧版・新版 数検協会発行の過去問題集 数検準1級 旧版・新版数検2級の過去問は通して1回解きました。そこで学習時間切れ。
数検準1級の過去問は、本格的には使わない前に合格したためパラパラ見た程度。 綴じ込み方式は残念ながら使いづらかったです。
(初稿 2008年3月4日)
(c) 2004-2014 必ず役に立つ体験記
|