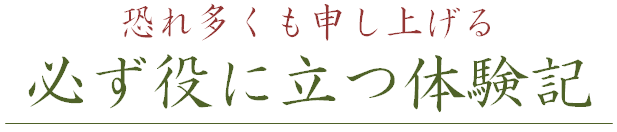|
身長の2倍 英書多読体験記
〈その1〉
今回の報告は、ジャパンタイムズ・伊藤サム氏提唱の「身長の2倍 英書多読」体験記です。「資格関連」ではありません。もともとそうですが、なおさら人様の役にはたちません。一人で盛り上がって第4信です。ですが、「楽しかったですよー!」と声を大にして言いたいのです。興味ある方だけ目をお通しくださるよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 やさたくから始めて、身長の2倍を達成 やさたくから始めて、身長の2倍を達成まず、ジャパンタイムズ伊藤サムさん、ありがとうございました。こういう目標設定が普通のおじさんにはわかりやすくて助かりました。単純に量ではかる!それも1倍でなく2倍、ここです!眼目は。
それにしても1倍達成したときに味わったがっかり感といったらありませんでしたよ。「エー、あともう1度この身長分あるのかよー・・・」、「ため息」を10回、20回つくほど遠い道のりに感じました。
ついでに申しますと、人によって身長が違うところがまたアナログでいいです。日頃の鬱憤晴らしではありませんが、小柄でよかった!(この選択をした場合、天命です。身長2メートルの人は4メートル読みましょう!あーすっきり。ここどうでもいいところです。背の高い人、熱くならないで下さい。)
くだらないことを書きました。本当は「身長の2倍・3メートルクラブ」などというグループ分けが妥当かもしれません。人によって尺度が違うのは結構辛いものです。伊藤サムさん、是非ご採用を!
 目標は334センチ 目標は334センチ167センチ×2=334センチメートルまで読みました。2001年2月27日〜3月18日の20日間でハリポタ①、326ページを読み上げて以来、2008年10月22日、フロスト警部シリーズ④、440ページを13日で仕上げ、7年8ヶ月です。すでに1.5倍までは報告させていただいたので、今回はその後1年半を経た感想です。
 この程度の実力で何とかなりました この程度の実力で何とかなりました2000年秋に英検準1級に合格し、しばらくして、TOEIC745点取り、以後実力はためしていませんが、いわゆる4技能あわせた総合力は伸びていません。断言するのも悲しいですが・・・
 原動力は「知りたい!」 原動力は「知りたい!」私の場合、ただの趣味ですので、選書の基準は「好奇心」。これに尽きました。言い直すと「知りたい!」ですね。ですから情緒の機微に訴える作品は相変わらずほとんど読みませんでした。そういいますとその通りではありますが、これではスノブの極みで、我ながら寂しいです。
 5000ページから7000〜8000ページへ 5000ページから7000〜8000ページへ昨年から今年にかけてようやく2倍のゴールが現実味を帯びてきましたので、スピードが上がってきました。
※ 分厚い本とは300ページ以上の本
無理を承知であえて傾向を見ると、初めは年5000ページ前後だったのが、次第に年6000ページ、7000ページとなってきています。内容としては、初期は多読本・やさたく本・児童書・薄い本が多く、今はほとんど大人の本・厚い本です。児童書で300ページを越したのはパフィンブックスの「赤毛のアン」と「若草物語」です。みせかけのページ数と実質のボリューム(語数)はだいぶ違いますのでスピードはさらに上がっています。
 連作の醍醐味を味わえました 連作の醍醐味を味わえました1.5倍〜2倍経過時はできるだけ連作に挑戦しました。例えば、
こういう形の楽しみ方を味わえたのは1.5倍以降の収穫でした。ようやく連山の向こうの風景が見え始めた気がしています。
 この本知っていますか?といいたくなる気持ち、ちょっとこたえられません この本知っていますか?といいたくなる気持ち、ちょっとこたえられませんときどきですが、世の中でまだ「きわきわしていない」本を読んで、おもしろかったときは、「自分だけが知っている感」を味わい、うれしかったです。
例えばオーストラリアの PAUL CARTERの本、「 Don't Tell Mum I Work on The Rigs 」(2005) 。石油掘削現場で働く若者の回想記。切れのいい文です。この職業でなければ見えてこない視点が新鮮です。
同じくオーストラリアの Rachel Tonkinの絵本 「 When I was a kid 」(1997)。電気屋のショーウインドウ越しに出始めたばかりのTVを見入るオーストラリアの人々。時は1956年。コートを着込んで、ポットにココアを入れて、折りたたみいす持参の家族連れ。犬まで同伴・・・
旅のついでに手に入れた本があんがいな掘り出し物だったとき誰かにいいたくてしかたなくなります。
 英語力は向上したか? 英語力は向上したか?英語そのものの力の伸びはまったく感じません。会話力など、会話専用テープを愛用していたころよりむしろ落ちています。そういう訓練をまったくしていないのですから当然です。連動しているといいのでしょうが、途中から、「読むこととその他の英語力とは別なこと」と割り切ってしまいました。いずれ飽きましたら、舵の向きを変えたいとは思いますが、この7年8ヶ月は、身長の2倍に至るので精一杯でした。現実の英語力向上を期待していた方はごめんなさい。
英語を楽しむという意味では最高でしたし、現在も次はこれを読もう、そう言えばあの本は・・・と予定が詰まっている状態です。考えたらそれで十分ですよね。
 1冊の中での読むスピードはどうか。 1冊の中での読むスピードはどうか。毎回そうですが、新しい本を読み始めて最初の30〜40ページが進みません。ようするにその話にまだ興味がわいていない。登場人物・場面設定からしてなじんでいないので進まない。単語もその本特有の単語になじんでいない。などなどのせいです。ですから半分を過ぎて、後100ページになったころはものすごい進み方になります。その結果、1日の読書スピードは、初日10ページ、中頃20〜25ページ、ラスト50ページ以上とだいたいなります。
 「100万語多読」はほぼハリポタシリーズ分 「100万語多読」はほぼハリポタシリーズ分この体験記自体がそうですが、物事を質だけで測ると辛いです。スポーツ・お稽古ごと・趣味すべて初心者にとっては質と量の兼ね合いで順調だったり、めげたりしながらまあ向上していくのですよね。ですから、最初から天才肌の人以外、量を日々の基準にするとリズムがつきます。リズムの中で先へ進むと、ときどき急激な進展があるのだと理解しています。ですから、量を測る適切な指針が大切です。その点、この「語数でモチベーションを高める方法」は多読の始めで、語数のリストができている本を読むときにはもってこいの方法です。
私の場合、偶然この体験記をハリポタシリーズ読破から始めました。あるときインターネット、アメリカサイト(Scholastic reading counts )で調べましたら、このハリポタ①から⑦までで総語数1,083,650語なのですね。あーそうか、「多読100万語達成」はだいたいハリポタの1セット分(1)と考えるとわかりやすいのだとそのとき私は納得し、100万語のボリュームを実感しました。実感するとともにこの指標で進度を測るレベルは卒業していいのかとも思いました。
(c) 2004-2014 必ず役に立つ体験記
|