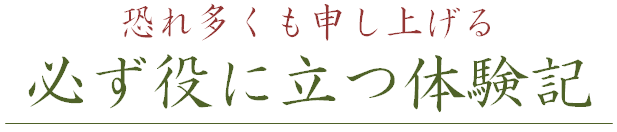|
鉄板の面白さ!「児童書300選」
〈その1〉
第8信です。はるか四半世紀前(平成2年3月)に出した、
当サイト管理人、初めての自費出版本が元です。
身内に配った典型例の本ですが、
ついでにこれも一部ですがインターネット公開してしまいます。
ご笑覧のほど。
そして、いつものこと、参考にならなくてもご容赦を!
舞台はある小さな学習塾です。
子育て真っ最中の中年のおっさんが代表でした(今はおじいさんになりました)。
毎月4冊づつ紹介して、5年間、60号まで続け、
読書通信「アトレーユ」という題にしてまとめたのです。
その後71号までさらに発行しましたが、そこで力尽き、中断しました(1)。
そのとき密かに思ったのです。
今に見ておれ、いずれ100号まで続けるぞ!と・・・
今、中断から四半世紀たち、とにかく4冊×71号で284冊(実質は350冊超)です。
人生いろいろありで中断のやむなきにいたりましたところまでで、
ずずずーいと、いやさ!大団円とござーい・・・・!
表現が今風に言いますと「上から目線」です。お許し下さい。
何しろ毎日接している生徒さんです。身内の鍛えなくてはいけない人材です。
半強制になるのはコーチと選手の関係で、しかたないのです。
その文体はいまさら変えられません。
これまた笑って許して下さい。
  読書通信「アトレーユ」 1号 読書通信「アトレーユ」 1号 クローディアの秘密 (1967→1975) クローディアの秘密 (1967→1975) 12歳のクローディアは家出するのです。何と博物館へ。
〔原作:E.L.Konigsburg, From The Mixedup Files of Mrs. Basil and FrankWeiler.〕  花咲か 岩崎京子 (1973) 花咲か 岩崎京子 (1973)時代は江戸後期。植木屋源吉のところへ奉公した主人公常七は要領よくなどできない若者。やがて彼が江戸を桜で満たす。
 肥後の石工 今西裕行 (1965) 肥後の石工 今西裕行 (1965) 眼鏡橋って知っていますか?アーチ型の石橋です。この特殊な技術を伝える江戸時代の石工たちの物語。教科書にもあります。
 クラバート オトフリート・プロイスラー 中村浩三訳 (1971→1980) クラバート オトフリート・プロイスラー 中村浩三訳 (1971→1980) ドイツ中世の話。「クラバート!シュバルツコルムの水車場へこい・・・」という不思議な夢を見た。魔法の使い手の親方とクラバートは・・・
  読書通信「アトレーユ」 2号 読書通信「アトレーユ」 2号 トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス 高杉一郎訳 (1958→1967) トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス 高杉一郎訳 (1958→1967)家の裏の扉を開けると、ないはずの庭があって・・・
 星空の狩人 関つとむ (1978) 星空の狩人 関つとむ (1978) 「セキ彗星」発見の記録。まるで自分が発見するような気持ちになって夢中で読める。自分を導いてくれた人達との暖かい交流には感動!
 銭五(ぜにご)とよばれた男 森下研 (1976) 銭五(ぜにご)とよばれた男 森下研 (1976) 江戸時代。加賀の少年五兵衛は海にあこがれる。やっと手に入れたぼろ船に乗り、大もうけを夢み、危険な航海に出る。
 はてしない物語 森下研 (1976) はてしない物語 森下研 (1976)今話題のネバーエンディングストーリーの原作。値段は高いけれども、自分のお正月のお年玉の残りをはたいてでも損はない。
  読書通信「アトレーユ」 3号 読書通信「アトレーユ」 3号 チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール作 田村隆一訳 (1964→1972) チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール作 田村隆一訳 (1964→1972)チャーリー少年は、家貧しくチョコレートを一年に一枚だけ誕生日に買ってもらえるだけ。あるとき不思議なチョコレート会社が特別のくじを5枚だけ自分の会社のチョコレートに入れた。
 たのしい川べーヒキガエルの冒険 ケネス・グレアム作 石井桃子訳 (1908→1963) たのしい川べーヒキガエルの冒険 ケネス・グレアム作 石井桃子訳 (1908→1963)時は春。場所はイギリス。たっぷりとした水がゴブリと静かに流れる川べ。もぐらが仕事を放り投げて走り出した・・・こういう友達がいるといい!
 縄文人の知恵にいどむ 楠本政助 (1976) 縄文人の知恵にいどむ 楠本政助 (1976) 縄文時代の人々はつりばりや、もりをどのようにして作ったのでしょう。いったいどんな魚を釣ったのでしょう。実験考古学を確立しつつある著者の自伝。
 フランバーズ屋敷の人々 K・M・ペイトン作 掛川恭子訳 (1967→1969) フランバーズ屋敷の人々 K・M・ペイトン作 掛川恭子訳 (1967→1969)みなしごになった12歳の少女クリスチナが伯父さんの家に行く。伯父さんの家には、従兄弟の乗馬好きのマークとまだ始めの時代の飛行機に夢をかけたウィリアムがいる。時代がやがて第一次世界大戦に突入するころの若者たちの夢は何だったのか。
  読書通信「アトレーユ」 4号 読書通信「アトレーユ」 4号 人形の家 ルーマー・ゴッデン作 瀬田貞二訳 (1947→1967) 人形の家 ルーマー・ゴッデン作 瀬田貞二訳 (1947→1967) 人形に心があるとしてみたら、その心で思ったことを人形はどうすることができるでしょう。自分たちの家をほしいと思ったら・・(大型本にはその家の見取り図があるよ)
 鉄を作る・色を染める・金属をさがす 大竹三郎 (1981~1983) 鉄を作る・色を染める・金属をさがす 大竹三郎 (1981~1983) 有名な「和同開珎」はなぜ発行されたのか?どうやったら鉄は作られたのか?私たちの祖先の知恵を知ろう。
 山の向こうは青い海だった 今江祥智 (1960) 山の向こうは青い海だった 今江祥智 (1960) 中学1年生の山根次郎は、はずかしいとすぐにが赤くなる気の弱い子でした。夏休みに自分をきたえるために大阪から紀ノ川ぞいの鷲もと市(どうやら和歌山県橋本市)に旅にでます。
 スマイラー少年の旅シリーズ スマイラー少年の旅シリーズビクター・カニング作 中村妙子訳 (1971~74→1979) Ⅰ チーターの草原 Ⅱ 灰色雁の城 Ⅲ 隼のゆくえ まちがいで犯人にされた少年スマイリーが三度の逃亡の間に出会う人たちがいい。イギリスの自然がなかなかいい。手に汗にぎる冒険がすごい。はたして犯人の汚名は晴らされるか?・・・・
  読書通信「アトレーユ」 5号 読書通信「アトレーユ」 5号 長い長いお医者さんの話 カレル・チャペック作 中野好夫訳 (1952→1962) 長い長いお医者さんの話 カレル・チャペック作 中野好夫訳 (1952→1962) 日本でいうと落語にこれと似たお医者さんが出てきますよ。ヨーロッパのカッパも出てきます。どんなカッパでしょうか。
 原生林のこうもり 遠藤公男 (1973) 原生林のこうもり 遠藤公男 (1973) 正規の教員でない代用教員として、半ば迷いながら山の分校に赴任して来た著者は、ふとしたきっかけから森のコウモリの生態に興味を持つ。ラストの場面にはこうもりなんて気持ち悪いと思う人も感動!
 イシ -二つの世界に生きたインディアンの物語- イシ -二つの世界に生きたインディアンの物語-シオドーラ・クローバー作 中野好夫・中村妙子訳 (1964→1977) 白人に滅ぼされ尽くし最後の7人だけが山深く隠れ住むヤヒ族インディアンの悲しい滅亡の記録。読んでいて心の底から悲しみがつきあげます。それでも最後まで読まずにはいられない不思議な記録です。最後の最後のヤヒ族イシはどうなる?
 ジェニイ(さすらいのジェニー) ジェニイ(さすらいのジェニー)ポール・ギャリコ作 古沢安二郎(矢川澄子)訳 (1950→1979・83) 突然ネコに変身してしまう8才の少年ピーターの冒険物語。作者ギャリコは、ネコの生態をよく知っている。まずそのことに本当にあきれますよ。ネコの話といっても、男の子にもおもしろいよ。
  読書通信「アトレーユ」 6号 読書通信「アトレーユ」 6号 メアリー・ポピンズのお話 P・L・トラヴァース作 林容吉訳 (1963~1965) メアリー・ポピンズのお話 P・L・トラヴァース作 林容吉訳 (1963~1965)
全部で36話あります。夏休み毎日一つずつ読むとちょうどいいかもね。メアリーポピンズという人は不思議な人です。一見少しもyさしくないのだけれど、いつもおこった顔をするのだけれど、すてきなんだなー。こんな人が先生だったらどうだい?
 ホタルの歌 原田一美 (1971) ホタルの歌 原田一美 (1971)ホタルなど知ってらーと言える人は何人いますか?考えてみると全然わかっていない夏の代表選手の話です。田舎に住んでいた著者たちでさえ、どこの卵を産み付け、どこで生活するのかすらわからなかったところから研究が始まります。
 ぼくがぼくであること 山中恒 (1969) ぼくがぼくであること 山中恒 (1969)兄弟はみなよくできる中で何をしてもへまなことになってしまう主人公秀一が、するつもりのなかった家出をしてしまい、かくれて乗ってしまったトラックが何と引き逃げをする・・・
 アーノルドのはげしい夏 J・R・タウンゼント作 神宮輝夫訳 (1969→1972) アーノルドのはげしい夏 J・R・タウンゼント作 神宮輝夫訳 (1969→1972)主人公アーノルド16才。さびれた村スカールストンの宿屋の息子。ところがある日、「本当は自分がアーノルドでおまえは別人だ」といいはる中年の男がずかずかと入ってくる・・・
  読書通信「アトレーユ」 7号 読書通信「アトレーユ」 7号 くまのパディントン マイケル・ポンド作 松岡享子訳 (1958~1964→1967~1977) くまのパディントン マイケル・ポンド作 松岡享子訳 (1958~1964→1967~1977)①くまのパディントン ②パディントンのクリスマス ③パディントンの一周年記念 ④パディントン フランスへ ⑤パディントンとテレビ ⑥パディントンの煙突掃除 ブラウン夫妻は駅でふと見つけたくま(これがかわいいんだなー)を家に引き取る。名付けてパディントン。ママレードが大好物。読んでいて「アーッ、今度こそはだめだ」と思っても妙にうまくいってしまう。みんなに好かれる子ぐまの話。43話。
 ツバメ号とアマゾン号 アーサー・ランサム作 岩田欣三・神宮輝夫訳 (1930→1967) ツバメ号とアマゾン号 アーサー・ランサム作 岩田欣三・神宮輝夫訳 (1930→1967)兄弟4人が夏休みに湖の無人島でキャンプをるすことを許される。しかも、ツバケ号というすてきなヨットまで使えて!どんな湖かは表紙の裏に地図があります。起こる冒険は何でしょう・・・
 台風の島に生きる -石垣島の先駆者・岩崎卓爾(たくじ)の生涯- 谷真介 (1976) 台風の島に生きる -石垣島の先駆者・岩崎卓爾(たくじ)の生涯- 谷真介 (1976)石垣島ってどこにあるか知っていますか?男子一生の仕事として、出世を考えず、島民とともに生きた測候所長の感動記録。
 ちょっとピンぼけ ロバート・キャパ作 井上清一・川添浩史訳 (1947→1978) ちょっとピンぼけ ロバート・キャパ作 井上清一・川添浩史訳 (1947→1978)著者は第二次世界大戦の従軍カメラマン。この本のカバーにキャパの一度見たら忘れられない顔写真があります。ピンぼけ写真を撮りそうな陽気な顔ですよ。暗い時代の一つの感動的記録!
  読書通信「アトレーユ」 8号 読書通信「アトレーユ」 8号 ナルニア国ものがたり C・S・ルイス作 瀬田貞二訳 (1950~1956→1966) ナルニア国ものがたり C・S・ルイス作 瀬田貞二訳 (1950~1956→1966)①ライオンと魔女 ②カスピアン王子のつのぶえ ③朝びらき丸 東の海へ ④銀のいす ⑤馬と少年 ⑥魔術師のおい ⑦最後の戦い 長い物語に挑戦したい人向き。合計1921ページあります。7つの物語は別々なのですが、全部まとめてまた一つの物語なのです。私は3が一番おもしろかったですよ。最後の少年達の結末は私には残念な形でした。あなた方はどう思いますか?
 埋(うず)もれた日本 たかし よいち (1975) 埋(うず)もれた日本 たかし よいち (1975)有名な大森貝塚や登呂遺跡などについての日本の考古学の黎明期(れいめいき)をいきいきと描いていて、縄文時代や弥生時代があなた方の身近になる。歴史が苦手な人に特に薦めます。
 暗闇(くらやみ)にうかぶ顔 暗闇(くらやみ)にうかぶ顔ジョーン・エイケン作 蕗沢(ふきざわ)忠江訳 (1969→1981) 主人公は女性。推理小説。題からして怖そうでしょう?記憶にない人の顔がなぜかはっきりと夢に出るのです・・・
 愛について ワジム・フロロム 木村浩・新田道雄訳 (1966→1973) 愛について ワジム・フロロム 木村浩・新田道雄訳 (1966→1973)発表された時の雑誌の発行部数は200万部。大変な反響を呼んで回し読みする順番ができたほどのソビエトの話です。御両親が別れてしまうのです。14才の主人公にそのことを誰も教えてくれないのです。君たちの心にまっすぐに向いた本。
  読書通信「アトレーユ」 9号 読書通信「アトレーユ」 9号 ピッピシリーズ アストリッド・リンドグレーン作 大塚勇三訳 (1945~48→1964~65) ピッピシリーズ アストリッド・リンドグレーン作 大塚勇三訳 (1945~48→1964~65)①長くつしたのピッピ ②ピッピ 船にのる ③ピッピ 南の島へ スウェーデンのお話です。牛も馬も頭上高く持ちあげてしまうという怪力を持った女の子、・・・その場でほら話を作り上げてしまう、学校にもいかないで、一人で生活している9才の女の子!大笑いしてしまうか、ばかばかしいと思うかはあなた次第。
 ならの大仏さま 加古里子(かこ さとし)作・絵 (1985) ならの大仏さま 加古里子(かこ さとし)作・絵 (1985)東大寺の大仏を知っていますか?この本は「歴史とはこんなにおもしろいのだ」ということをわからせてくれます。絵本ですが、大人でも思わずうなるほどです!3の②と比べるとよい。
 シリーズ・日本人はどのように建造物をつくってきたか シリーズ・日本人はどのように建造物をつくってきたか
イラスト絵本です。②は「奈良の大仏さま」と違う立場な所があります。比べて読むことのおもしろさを味わったら?③は天下の名城の出来るまでとその後がイラストのおかげで真に迫る。
 燃えるアッシュ・ロード アイバン・サウスオール作 小野章訳 (1965→1980) 燃えるアッシュ・ロード アイバン・サウスオール作 小野章訳 (1965→1980)オーストラリアの少年3人組がキャンプの火の不始末から山火事をおこしてしまう。それが想像を越す大きな山火事となり、思いがけない出来事に次々と発展していく。いったいこの山火事はどうなるか?
  読書通信「アトレーユ」 10号 読書通信「アトレーユ」 10号 イシダイしまごろう 菅能琇一作 渡辺可久絵 (1974) イシダイしまごろう 菅能琇一作 渡辺可久絵 (1974)本州中部から南部にかけて多く見られる代表的ないそ魚であるイシダイの話です。誕生から水族館の人気者になるまでが暖かい書き方で書かれています。ほのぼのとした気持ちになるよ。
 パール街の少年たち モルナール作 宇野利泰訳 (1907→1976) パール街の少年たち モルナール作 宇野利泰訳 (1907→1976)ハンガリーの首都ブダペストの少年たちの話。製材工場の空き地(原っぱ)をめぐる痛快な陣取りごっこ!対するは植物園を本拠地にする赤シャツ団。しかし、その空き地も・・・  坊ちゃん 他 夏目漱石作 (1906→1985) 坊ちゃん 他 夏目漱石作 (1906→1985)全集形式のひとつの例として薦めます。ここまで注釈をつけたならとにかく「坊ちゃん」が読めるはずです。シリーズ物の善し悪しはある程度配本が進んでこないとわかりませんが、この10月に第一回配本だということを尊重したいと思います。
 王のしるし ローズマリ・サトクリフ作 猪熊葉子訳 (1965→1973) 王のしるし ローズマリ・サトクリフ作 猪熊葉子訳 (1965→1973)紀元前後のローマ帝国華やかなりし時代のカレドニア族とダルリアッド族が勢力を争っていたスコットランドの物語。奴隷の出である剣闘士フィドルスは親友との死闘の末やっと克ちとった自由をその日からもてあます。しかし彼が、ローマ支配の地のかなたエラ=ギルのダルリアッド族の王統マイダーに顔形が似ていたことから、ふとした縁でマイダーの身代わりを務める。王位を簒奪された非力な氏族ドルリアッドの運命がこの身代わりの王フィドルスの肩にやがて重くのしかかってくる。人の生きる意味を重厚に問いかけて読む人を離さない。これまでの読書通信中で最も本格派の作品ではないかな・・・
  読書通信「アトレーユ」 11号 読書通信「アトレーユ」 11号 赤ノッポ青ノッポ 武井武雄 (1934→1982)
赤ノッポ青ノッポ 武井武雄 (1934→1982)昭和9年作。50年以上前のほのぼのとした漫画を味わって下さい。不思議な不思議な味わいがあるのです。実は私が子供のとき(50年前ではないよ!)何十回もあきずに見た漫画です。  インガルス一家の物語
インガルス一家の物語ローラ・インガルス・ワイルダー作 恩地三保子訳 (1932~1939→1972・3) 1 大きな森の小さな家 2 大草原の小さな家 3 プラム・クリークの土手で 4 シルバー・レイクの岸辺で 5 農場の少年 テレビで有名ですが、原作の味わいはまた違います。一作一作アメリカの開拓時代の光景が浮かび上がってすばらしい。
 シリーズ・日本人はどのように建造物をつくってきたか
シリーズ・日本人はどのように建造物をつくってきたか
先回に続いてイラスト絵本です。現存する世界最古の木造建築である法隆寺。そして東京の前身江戸の出来るまでについてです。特に江戸の町(上)(下)は、どの1ページも見ていてあきません。  指輪物語 J・R・R・トールキン作 瀬田貞二訳 (1954~1955→1972)
指輪物語 J・R・R・トールキン作 瀬田貞二訳 (1954~1955→1972)旅の仲間(上・下) 二つの塔(上・下) 王の帰還(上・下) 長~い、。長~い話です。これまでの最長のページ数です。現実とは何の関係もない話ですがから、本から知識を得ようという人には向きません。できる限りおもしろくて長い本を読みたい人向きです。ホビットという架空の小人族の一人フロドが不思議なえにしで所有する「総てを統べる指輪」をその危険さ故に永久に捨ててしまうために危険な旅にでるのです。そこから先の半紙は自分で味わって下さい。一巻ごとの地図か良いのです。次から次へと出てくる英雄にはうれしくなる!
  読書通信「アトレーユ」 12号 読書通信「アトレーユ」 12号 町かどのジム エリノア・ファージョン作 松岡享子訳 (1934→1965)
町かどのジム エリノア・ファージョン作 松岡享子訳 (1934→1965)引退した船乗りジムの8つの冒険話がつまっています。例えば霧で動けなくなった船のマストの上におぼると霧が下に海のようになっていて、向こうの霧の上には島が見える「ありあまり島」という話などいかが?  絵で見る 日本の歴史 西村繁男 (1985)
絵で見る 日本の歴史 西村繁男 (1985)ズバリ絵本です。横開きで縦26㎝、横60㎝あります。まさに絵巻物です。じっくり細かい部分まで見ていくと本当にあきません。幼稚だと馬鹿にしないことですよ!  ジャガイモの花と実 板倉聖宣 (1968)
ジャガイモの花と実 板倉聖宣 (1968)ジャガイモの実って知っていますか?花はどうですか?「 馬鈴薯の うす紫の花にふる 雨を思へり 都の雨に 」という短歌があります。どこの国が原産ですか?だんぜん楽しい本です。  ウォーターシップ・ダウンのうさぎたち
ウォーターシップ・ダウンのうさぎたちリチャード・アダムズ作 神宮輝夫訳 (1972→1975) 弱いものの代名詞にされているうさぎですが、弱いものの死にものぐるいの行動に手に汗握ります。決断力のあるヘイズル、予知能力のあるファイバー、勇敢なビグウィグなど、一匹一匹のうさぎたちが個性豊かに自分たちうさぎの生き残りをかけて大活躍します。10年ほど前に大人の世界でベストセラーになったのですが、中2以上なら読めます。
  読書通信「アトレーユ」 13号 読書通信「アトレーユ」 13号 銀のうでのオットー ハワード・パイル作 渡辺茂夫訳 (1983→1988)
銀のうでのオットー ハワード・パイル作 渡辺茂夫訳 (1983→1988)ドイツ中世の話。オットーという男爵家の世継ぎがなぜ銀の腕と呼ばれるか?運命と光さす結末。中世が身近になる!  トロッコ・鼻 他 芥川龍之介 (1915~1922)
トロッコ・鼻 他 芥川龍之介 (1915~1922)中学受験勉強の際、皆一度は目を通します。「羅生門」「鼻」「戯作三昧」「蜘蛛の糸」「蜜柑」「杜子春」「トロッコ」等すべて短編ですし、この本には未掲載の「芋粥」も含めて離しのおもしろさは抜群です。ところでこれらの作品の題名全部読めましたか?  あしながおじさん J・ウェブスター作 坪井郁美訳 (1912→1970)
あしながおじさん J・ウェブスター作 坪井郁美訳 (1912→1970)言わずと知れた「あしながおじさん」と言いたいのですが、案外読んでいないのかな?初めて読んだときのひとときの幸福感は読んだ人だけが共有できます。だからあらすじは内緒です。  Daddy-Long-legs Jean Webster (1912)
Daddy-Long-legs Jean Webster (1912)まだ複雑にならない時代のアメリカの良心なのでしょうね。教養が生きていた時代の女子教育というやつかもしれません。今では不思議な
教育なのでしょうかねー。ですが、なぜかいい。  ハチの生活 (1974)/昆虫学50年(あるナチュラリストの回想) (1976) 岩田邦雄
ハチの生活 (1974)/昆虫学50年(あるナチュラリストの回想) (1976) 岩田邦雄地球上に現存する昆虫は、100万種を越しています。その内の20万種はハチなのだそうです。何と種類の多い昆虫でしょう!ファーブルの弟子とあだなされ、ハチに魅せられて、3年制の旧制高校を5年かけて卒業した著者の、緻密かつ詳細な観察記とユニークな自伝。
  読書通信「アトレーユ」 14号 読書通信「アトレーユ」 14号 せいめいのれきし バージニア・リー・バートン作 いしいももこ訳 (1962→1964)
せいめいのれきし バージニア・リー・バートン作 いしいももこ訳 (1962→1964)太陽の誕生から、生物の発生、生物の海から陸への上陸、は虫類の出現・・・と、どのページも見ていて本当に楽しいですよ。  モモ ミヒャエル・エンデ作 大島かおり訳 (1973→1976)
モモ ミヒャエル・エンデ作 大島かおり訳 (1973→1976)「時間どろぼうとぬすまれた時間を人間にとりかえしてくれた女の子のふしぎな物語」とある、「はてしない物語」の著者の作。  二年間の休暇 ジュール・ベルヌ作 朝倉剛訳 (1888→1968)
二年間の休暇 ジュール・ベルヌ作 朝倉剛訳 (1888→1968)「十五少年漂流記」と言う別名の方が有名ですが、本格派の訳は断然こちらです。ニュージーランドの子供たちが乗った船が漂流し、南アメリカの無人島に着く。15人の少年たちはその島でどうなる?  しろばんば 夏草冬濤(なつぐさふゆなみ) 井上靖 (1915~1922)
しろばんば 夏草冬濤(なつぐさふゆなみ) 井上靖 (1915~1922)小学生時代を今からおよそ70年前、大正初期の伊豆の湯ケ島ですごした著者の自伝的小説。君たちのおじいさん、おばあさん方がかつて同じようであった生活なのです。読み進むに連れて主人公浩作少年の心の動きに一体感を感じてきます。興味ある人は続巻にあたる「夏草冬濤」もありますが、おもしろさは中程度です。
  読書通信「アトレーユ」 15号 読書通信「アトレーユ」 15号 おばけ桃の冒険 ロアルド・ダール作 田村隆一訳 (1961→1972)
おばけ桃の冒険 ロアルド・ダール作 田村隆一訳 (1961→1972)主人公ジェームス・ヘンリー・トロッターのお父さん・お母さんはサイに食べらてしまったのだそうです。いきなり1ページ目の所でですよ。  怪盗ルパン/ルパン対ホームズ/奇岩城
怪盗ルパン/ルパン対ホームズ/奇岩城モーリス・ルブラン作 榊原晃三訳 (1907・1908・1909→1983) あの有名なルパンの物語です。ルパンのかっこよさにはまいってしまいますね。盗めるはずのない宝石が盗めてしまうし、抜け出せるはずのない監獄から脱獄してしまう。「怪盗ルパン」。シャーロック・ホームズというこれまた超有名な探偵(この人を主人公にした作品は本当はコナン・ドイルという人が著しています。そちらもいずれ紹介します。)と闘う「ルパン対ホームズ」。若き高校生ボートルレと推理とトリックを競い合う「奇岩城」。どれも息もつかせぬおもしろさです。興味のある人、他にルパンの全集もありますよ。  ドクトルマンボウ昆虫記 北杜夫 (1961)
ドクトルマンボウ昆虫記 北杜夫 (1961)北杜夫のシリーズ物は軽妙なジョークにあふれています。どれから読み始めてもいいのですが、これは受験問題によく登場します。  外国語上達法 千野栄一 (1986)
外国語上達法 千野栄一 (1986)よくある英語だけの上達法と一味違っています。けっしてビックリすることは書かれていませんが、信じて勉強することが一番です。
(c) 2004-2014 必ず役に立つ体験記
|