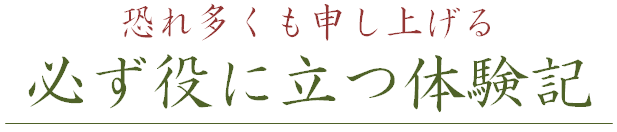|
鉄板の面白さ!「児童書300選」
〈その2〉
 読書通信「アトレーユ」 16号 読書通信「アトレーユ」 16号 大どろぼうホッツェンプロッツ/ふたたびあらわる/三たびあらわる 大どろぼうホッツェンプロッツ/ふたたびあらわる/三たびあらわるオトフリート・プロイスラー作 中村浩三訳 (1962・1969・1973→1966~1975) 読み始めると一気に3冊読んでしまうでしょう。ホッツエンプロッツというどろぼうと二人の少年たちのゆかいなシリーズです。  ハイジ ヨハンナ・シュピーリ作 矢川澄子訳 (1880→1974)
ハイジ ヨハンナ・シュピーリ作 矢川澄子訳 (1880→1974)アルプスの少女ハイジといったら知らない人はいないのでは?両親をなくしたハイジが祖父アルムじいさんに預けられる。そこは、羊飼いのペーター少年しか通って来ないスイスアルプスの山の上。暮らしていけるところなのだろうか・・・  Heidi Johanna Spyri (1880)
Heidi Johanna Spyri (1880)こういうストーリーこそ鉄板でしょう。子供時代に浸れた人は幸せです。英書慣れの時期に文句なくおもしろい。  クマゼミの島 島本寿次 (1972)
クマゼミの島 島本寿次 (1972)セミはについての生態研究は案外すすんでいないのですね。クマゼミは日本の西南地方にのみ分布しているセミです。大きな体でシャーシャーと鳴く様子は壮観です。瀬戸内海の岩黒(いくろ)島の小中学校の生徒たちの昭和43年から数年間のすばらしい研究記録です。  父の詫び状 向田邦子 (1878)
父の詫び状 向田邦子 (1878)女性の鋭い感性で記録した人生のスケッチ集です。大人が読むと思わずホロリとしてしまう?そういうタイプの一級品の随筆ですが、君たちにとってはどうなのでしょう。少し早いかと思うのですが、受験問題には打って付けの作品集なのです。まあ、どうぞ。
  読書通信「アトレーユ」 17号 読書通信「アトレーユ」 17号 ドリトル先生物語全集
ドリトル先生物語全集ヒュー・ロフティング作 井伏鱒二 (1920~1952→1961・62)訳
①ドリトル先生アフリカゆき ②ドリトル先生航海記 ③ドリトル先生の郵便局 ④ドリトル先生のサーカス ⑤ドリトル先生の動物園 ⑥ドリトル先生のキャラバン ⑦ドリトル先生と月からの使い ⑧ドリトル先生月へゆく ⑨ドリトル先生月から帰る ⑩ドリトル先生と秘密の湖 ⑪ドリトル先生と緑のカナリア ⑫ドリト先生の楽しい家 読み出すとやめられません。全集は何と12巻!私は大好きになりました。読んでいた一月半ほどがあっと言う間でした。  マルコ・ポーロの冒険
マルコ・ポーロの冒険ピエロ・ベントゥーラ絵 ジアン・パオロ・チェゼラーニ文 吉田悟郎訳 (1977→1982) イタリアの歴史絵本です。なるほどイタリアの絵本だと感じ入るほど絵がすてきです。ただし、書かれてあることは高度です。世界の歴史に親しむチャンスです。 マルコポーロ(1252~1324)。  石切り山の人々 竹崎有斐(ゆうひ) (1976)
石切り山の人々 竹崎有斐(ゆうひ) (1976)昭和61年の開成中学入試に出題された物語です。というと難しいと思うでしょうが、ガキ大将、権六少年の成長物語です。  さぶ 山本周五郎 (1963)
さぶ 山本周五郎 (1963)江戸時代。芳古堂(ほうこどう)という経師屋(きょうじや)に住み込む職人、栄二とさぶの友情物語。栄二の無実の罪をめぐっての人々の様々な行動。栄二自身の変化が見物。
  読書通信「アトレーユ」 18号 読書通信「アトレーユ」 18号 ケストナー少年文学全集 エーリッヒ・ケストナー (1976)
ケストナー少年文学全集 エーリッヒ・ケストナー (1976)
①エミールと探偵たち ②エーミールと三人のふたご ③点子ちゃんとアントン ④飛ぶ教室 ⑤五月三十五日 ⑥ふたりのロッテ ⑦わたしが子どもだったころ ⑧動物会議 ⑨サーカスの小びと ケストナーはドイツの作家。題名だけでも変でしょう。どの作品もユーモアと涙あり、です。  コロンブスの航海
コロンブスの航海ピエロ・ベントゥーラ絵 ジアン・パオロ・チェゼラーニ文 吉田悟郎訳 (1977→1979) 同じシリーズの前回のマルコポーロに続いての紹介です。コロンブスは実はマルコ・ポーロの言う黄金の島ジパング(日本)へ行くことをめざして西に航海し、その結果バハマ諸島を発見した。等、本文に新知識が一ぱいです。特に新大陸が起源の植物の一覧がすごい。  二十四の瞳 壺井栄 (1952)
二十四の瞳 壺井栄 (1952)瀬戸内海小豆島の一分教場の12人の新一年生とその先生大石先生の昭和3年の春、4月から昭和21年麦秋までの物語。すてきな新米先生だった大石先生が戦争をはさんで年をとっていく。12人の一年生とて同じです。国語の教科書で有名な「石臼の歌」の著者にまた会えます。  バルセロナ石彫り修行 外尾悦郎(そとお えつろう) (1985)
バルセロナ石彫り修行 外尾悦郎(そとお えつろう) (1985)25歳の年に故郷日本を後にした彫刻家の7年間の修行体験です。ガウディという建築家の作り始めたサグラダ・ファミリア教会の彫刻担当に採用されて、重要な仕事をまかされるまでの痛快な青春期。
  読書通信「アトレーユ」 19号 読書通信「アトレーユ」 19号 クヌギ林の24時間 海野和男 文・写真 (1979)
クヌギ林の24時間 海野和男 文・写真 (1979)雑木林のクヌギなどの木の樹液が幹の表面にしみ出ると微生物の働きであまずっぱくてちょっぴりお酒がはいっているような液になります。そこに集まるカブトムシなどの昆虫の24時間の観察記です。「昆虫はなぜ光に集まるか」という説明など興味深い話が満載!  マゼランの航海
マゼランの航海ピエロ・ベントゥーラ絵 ジアン・パオロ・チェゼラーニ文 吉田悟郎訳 (1979→1981) 歴史上初めて世界一周をしたマゼランはポルトガル人だったがポルトガルの王ではなく、スペインの王の援助で計画を実行に移した。ここに後の遠征中の不幸の元があった。話は、巨人の土地、別の大洋へつながる海峡発見、引き潮の悲劇、270人が18人へ・・・など。  神秘の島 ジュール・ベルヌ作 清水正和訳 (1877→1978)
神秘の島 ジュール・ベルヌ作 清水正和訳 (1877→1978)時代はアメリカ南北戦争の真最中の1865年。南軍に捕虜になっていた身から気球で脱走を試みた5人の男は、嵐の中を逃げのび、何と太平洋のまっただ中のなぞの陸地にたどりつく。そこでロビンソン・クルーソーのように自活しだすが、生活すればするほど、ここには誰か自分たち以外に人がいるのでは?という気がしてくる・・・  路傍の石 山本有三 (1937)
路傍の石 山本有三 (1937)「路傍の石」と「吾一」の名は、かつて知らない人が日本に一人もいなかったのです。作中で、少年吾一が鉄橋にぶらさがる場面がかつての読者の興味をわしづかみにしたのです。吾一が成長する姿が共感できますよ。吾一の名については小学校の校長先生の口を借りて紹介されますが、路傍の石、つまり「道の端っこにある石」という象徴的な題名は本文中では最後まで説明されません。
  読書通信「アトレーユ」 20号 読書通信「アトレーユ」 20号 ウニ 《5億年の歴史をきざむ》 鈴木克美 (1978)
ウニ 《5億年の歴史をきざむ》 鈴木克美 (1978)著者は「これはウニの本です。けれどもウニだけの本ではないつもりです。」と言う。さて質問。「ウニに脳はあるか?ウニの未来は?」「なぜウニは5億年も繁栄し続けていられたか?」わかりますか?  元気のさかだち 三木卓 (1986)
元気のさかだち 三木卓 (1986)今から40年以上前の少年のことです。ですが、「あっ、こんなやつ、いるいる」「こういう気持ち、わかるんだよなあ」と君たちもきっと思うほど身近に書かれています。題名がいい。監察なしの魚釣りと監視人「かんじい」の不思議な友情の話がいい。パラパラ映画(わかる?)の映画きちの友人の話がいい。思わずつりこまれ、時にはほろりとする。  太陽の戦士 ローズマリ・サトクリフ作 猪熊葉子訳 (1958→1968)
太陽の戦士 ローズマリ・サトクリフ作 猪熊葉子訳 (1958→1968)場所はイギリス。時代は男たちが戦士としてやりや弓を持った青銅時代。主人公ドレムは片腕が不自由であった。戦士になるための狼との死闘を盾なしに勝ち抜くとは誰も考えていなかった。事実、血のにじむ努力にもかかわらず、運命のちょっとしたいたずらで彼は戦士にはなれなかったばかりではなく・・・手に汗にぎる大傑作。  赤毛のアン モンゴメリ作 村岡花子訳 (1908→1954)
赤毛のアン モンゴメリ作 村岡花子訳 (1908→1954)舞台はカナダ。孤児院から一人の女の子が農家のクズバート家にもらわれる。赤毛でそばかすだらけの空想好きな少女アン。次から次へと失敗するが、まわりの人をいつのまにか友達にする。話は少女から学校の先生になるところまで。きっと読み終わるのがおしい気がし、読み終わって幸せなひとときが味わえますよ。続編あり。  Anne of Green Gables L. M. Montgomery (1925)
Anne of Green Gables L. M. Montgomery (1925)はずせません。活発で饒舌な女の子、いつの時代でもあこがれます。
  読書通信「アトレーユ」 21号 読書通信「アトレーユ」 21号 トテ馬車 千葉省三 (1925~35)
トテ馬車 千葉省三 (1925~35)『虎(とら)ちゃんの日記』や『タカの巣とり』という作品が特に有名ですが、ここに収められた17の作品はどれもなぜかなつかしい思いで読まされます。君たちにとってはひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんの時代のいなかの子どもの生活です。『しろばんば』よりはずっとユーモアがありおもしろいですよ。  秘密の花園 F・E・バーネット作 猪熊葉子訳 (1911→1977)
秘密の花園 F・E・バーネット作 猪熊葉子訳 (1911→1977)『小公子』『小公女』の作者のもう一つの有名な古典。主人公メリーは、わがまましか知らないいやな9歳の女の子。両親がなくなり、使われていない部屋が100もある屋敷に住むおじさんに引き取られる。その家の秘密。入ることのできない庭。どこかで聞こえる子どもの泣き声・会えないおじさん・・・ぞくぞくしないかい?  空を飛ぶクモ 錦三郎 (1974)
空を飛ぶクモ 錦三郎 (1974)山形県の米澤盆地ではそろそろ雪がこようとするころ白い細い糸のようなものが空を流れていきます。人々はこれを「雪迎え」と言っていました。その正体を知るまでに著者は13年かかったのです。  青いひれ コリン・シール作 犬飼和雄訳 (1958→1981)
青いひれ コリン・シール作 犬飼和雄訳 (1958→1981)オーストラリアのまぐろ船「青いひれ号」の船長の息子スヌークは高校1年生。初めて父親の船に同乗できたとき、大事なところで船から転落してしまい、父から遠ざけられる。だが、不漁と借金のためこれが最後の航海かもというときになり、乗り組む者がいないためスヌークも再び船にのれる。しかし、そこで待っていた運命は・・・
  読書通信「アトレーユ」 22号 読書通信「アトレーユ」 22号 かいこ 熊谷元一 文・絵 (1973)
かいこ 熊谷元一 文・絵 (1973) カイコの一生 佐々木崑 写真・文 (1980)
カイコの一生 佐々木崑 写真・文 (1980)『かいこ』の方は、日本の農村で大切に作り続けられてきた雰囲気がよくできた絵本です。『カイコの一生』は写真版ですのでカイコガの写真など、よくも悪くもよくわかります。ぜひどうぞ。  シャーロットのおくりもの E・B・ホワイト作 鈴木哲子訳 (1952→1973)
シャーロットのおくりもの E・B・ホワイト作 鈴木哲子訳 (1952→1973)アメリカのいなかの農家に生まれた未熟児のぶたのウィルバーが、ハムやソーセージにされないで暮らせるように友だちのくものシャーロットとねずみのテムプルトンが苦心する。さし絵がかわいらしく、ぶたもとてもあいきょうがあり、ほのぼのとしてきます。それでいて生きることの大切さと死の重みが全編から伝わって来るえがたい物語です。  ニワトリ号一番のり ジョン・メイスフィールド 作 木島平治郎訳 (1911→1967)
ニワトリ号一番のり ジョン・メイスフィールド 作 木島平治郎訳 (1911→1967)若い二等航海士クルーザーが乗ったチャイナ・クリッパーは中国から新茶をつんで、他の三そうと競争しながらイギリスへ向かっていたが、霧の中で他の船と衝突し、沈没してしまう。幸い、おんぼろボートに乗れたクルーザーたち生き残りはそのボートを必死に走らせるが・・・  走れメロス 太宰治 (1940) 講談社少年少女日本文学館
走れメロス 太宰治 (1940) 講談社少年少女日本文学館 山椒魚 井伏鱒二 (1923) 講談社少年少女日本文学館<
山椒魚 井伏鱒二 (1923) 講談社少年少女日本文学館<共に超有名な作品です。
推薦理由1-私は、仮名がふってあることのありがたさにいささか感動しました。「ああ、そう読むのか!と初めて知った読み方が『走れメロス』中何件もありました。」 推薦理由2-太宰治の師である井伏鱒二に注目して欲しいのです。『遙拝隊長』は大人の読書への橋渡しです。   読書通信「アトレーユ」 23号 読書通信「アトレーユ」 23号 カンポンのガキ大将 ラット作 荻島早苗・末吉美栄子訳 (1979→1984)
カンポンのガキ大将 ラット作 荻島早苗・末吉美栄子訳 (1979→1984)著者のラットはマレーシアの人気漫画家です。マレーシアという国は近くて遠い国の一つなのですが、この漫画は笑いと涙ありで抜群です。ついでに、マレーシアと言ったらゴムと錫(すず)、宗教はイスラム教といったことが自然にわかります。カンポンとはマレーシア語で「村」のことです。  ぼくの村が消える アニタ・デサイ作 岡本浜江訳 (1982→1984)
ぼくの村が消える アニタ・デサイ作 岡本浜江訳 (1982→1984)インド西岸の大都市ボンベイからわずか14㎞にあるトゥールという村に住んでいる13歳のリラと12歳のハリという姉弟が主人公です。インドという国も知っているようで知らない国ですが、なるほど今のインドはこうかと少し納得します。それよりも、ハリが村から出て苦労して自分の職業を決めるまでなど、話そのものがおもしろい。  シャーロック・ホウムズの冒険
シャーロック・ホウムズの冒険コナン・ドイル作 林克己訳 (1852~1905→1955~1976)
①シャーロック・ホウムズの冒険
②シャーロック・ホウムズの回想 ③シャーロック・ホウムズ 帰る 15号で紹介したルパンと好一対の有名な作品です。ウォトスン(ワトソン)というという医者を相棒に推理で事件次々に解決するシャーロック・ホウムズ。私は『青い紅玉』という作品が一番好きでした。どんな話ですかって?秘密、秘密。  英語辞書の使い方 外山滋比古 (1983)
英語辞書の使い方 外山滋比古 (1983)最近の中学生は英語の辞書を引かなくなった。と誰もがいいます。ではどうすればいいか?著者は、辞書が意外に「おもしろい」ものであることを知ってもらうのが早道だと考えてこの本を書いたそうです。fingerは8本という話などあれっと思うでしょう?
  読書通信「アトレーユ」 24号 読書通信「アトレーユ」 24号 がんばれヘンリーくん ベバリイ・クリアリー作 松岡享子訳 (1950→1968)
がんばれヘンリーくん ベバリイ・クリアリー作 松岡享子訳 (1950→1968)主人公は小学3年生。アバラーという名前の犬を拾います。バスに乗せて連れ帰ろうとして大騒ぎの巻。大安売で買ったグッピー2匹が育てると100匹になってしまい、飼うに困って売ると、何と7ドルで売れた巻。など身近な楽しい話でいっぱい。シリーズあり。  トム・ソーヤーの冒険 マーク・トウェイン作 大塚勇三訳 (1876→1975)
トム・ソーヤーの冒険 マーク・トウェイン作 大塚勇三訳 (1876→1975)有名なトム・ソーヤーの話です。よく英語の教科書にあるへい塗りの話。カードとひきかえに聖書と栄光を手にする日曜学校の話。家出して海賊ごっこをする話。洞穴の中で迷い、死にかける話。読み直していて、どれもなつかしく、夢中になって再読しました。昔読んだから今なつかしいのですね。エイブ・リンカーンと同時代。  ロールパン・チームの作戦 E・L・カニグズバーグ作 松永ふみ子訳 (1969→1974)
ロールパン・チームの作戦 E・L・カニグズバーグ作 松永ふみ子訳 (1969→1974)主人公は12歳。リトル・リーグ野球の選手を目指すが、何と自分のチームの監督に自分のママがなってしまう!おまけにコーチはママの氏名で兄さんのスペンサーときては、あなただったら「ばんざい」ですか?さらに加えてチームは昨年は連敗チーム。スコアは14対0とか21対3という調子。いったいこのマークとチームはどうなる・・・  エイブ・リンカーン 吉野源三郎 (1967)
エイブ・リンカーン 吉野源三郎 (1967)この本は、奴隷解放宣言や、「人民の、人民による、人民のための政治」という言葉で有名なリンカーン(1809~1865)の本格の伝記です。かねて本格だと聞いていましたが、読んでみて納得しました。若いときの苦労話やきさくな逸話(いつわ)がおもしろいよ。
  読書通信「アトレーユ」 25号 読書通信「アトレーユ」 25号 たおされたカシの木 吉見昭一 著 石部虎二 絵 (1976)
たおされたカシの木 吉見昭一 著 石部虎二 絵 (1976)ある枯れかけたカシの木が杜の土になっていくまでのキノコの働きを昭和42年秋から48年春まで追った記録です。まだ、葉がしげっていた木がキノコの働きで見事に土になってします経路にはほんとうにビックリさせられます。  オタバリの少年探偵たち セシル・デイ・ルイス作 瀬田貞二訳 (1948→1957)
オタバリの少年探偵たち セシル・デイ・ルイス作 瀬田貞二訳 (1948→1957)戦争ごっこに夢中になっている二つの少年たちのグループの一人ニックが教室の窓ガラスを割ってしまう。校長先生は弁償するよう命じるが(この学校厳しいねー)、ニックにはそのお金がない。そこで仲間は寄付の募金を町の人から募るという案を考え出す。そうしてせっかく集めた大金が何と盗まれてしまった!  わたしの動物記 増井光子 (1974)
わたしの動物記 増井光子 (1974)著者は当時の多摩動物公園の獣医さん(後上野動物園の園長さん)。あきずに一気に読める本の絶好例です。ラクダのこぶには何がつまっているかの話。94日えさを食べなかったアザラシの話。しっぽは何のためにあるかの話。など知識としておもしろく、しかも人間のふるまいへの反省にもなる。  項羽と劉邦(こううとりゅうほう) 司馬遼太郎 (1980)
項羽と劉邦(こううとりゅうほう) 司馬遼太郎 (1980)これは痛快な本です。中学の歴史の教科書ではたった3行しか書かれていない秦から漢帝国への歴史を項羽と劉邦という二人の英雄の戦いとして描いた歴史小説です。100戦して100敗する劉邦が勝つのです。背水の陣、四面楚歌、虞美人草(ぐびじんそう)などの言葉はこの二人の戦いからとられたのです。
  読書通信「アトレーユ」 26号 読書通信「アトレーユ」 26号 ガラスのエレベーター宇宙にとびだす ロアルド・ダール作 田村隆一訳 (1972)
ガラスのエレベーター宇宙にとびだす ロアルド・ダール作 田村隆一訳 (1972)『チョコレート工場の秘密』の続編です。ガラスのエレベーターなどがどうして登場するかは前作を読んで下さい。宇宙船とのドッキングやら、宇宙飛行士救助の話、一粒で20年若くなる薬でマイナスの国に行ってしまったり・・・とあれよあれよという間に話に引き込まれます。  若草物語 L・M・オルコット作 矢川澄子訳 (1868→1957)
若草物語 L・M・オルコット作 矢川澄子訳 (1868→1957)みんな題名は知っていますね。私はこの本はこれで3度目の通読になりますが、どういうわけか、毎回あらすじが思い出せなくなります。今回は、読んでいて「そうか、これは少女漫画の原型なわでだ!」と感じいりました。だからね、漫画が好きな女の子はぜひ読むといいよ!  少年朝日年鑑・社会 朝日新聞社 (1983)
少年朝日年鑑・社会 朝日新聞社 (1983)社会の受験勉強の際の座右の書(意味わかる?)です。毎年買う必要はないでしょうが、中学・高校受験生は受験の年には自分で買って読むべきですね。特に統計編が良く、高度な統計をふりがなつきでわかりやすく図解しているので見ていてあきません。  フランクリン自伝 ベンジャミン・フランクリン著 鶴見俊輔訳 (1868→1966)
フランクリン自伝 ベンジャミン・フランクリン著 鶴見俊輔訳 (1868→1966)例えば昭和60年度の明大中野高校入試問題の英語の1番はフランクリンの伝記を題材にしています。クラウンの中3英語教科書にもフランクリンは登場しています。本業は印刷屋です。雷の正体は電気だと発見した人です。アメリカ建国の父なのです。その他、その他、実にユニークな考え方、生き方をした人です。この自伝は現代に通用しますよ。
  読書通信「アトレーユ」 27号 読書通信「アトレーユ」 27号 ぼくの昆虫記 浜野栄次 (1985)
ぼくの昆虫記 浜野栄次 (1985)有名な昆虫写真家の書いた昆虫記です。ページの量の少ない本ですから、さっと一日で読めます。今活躍している人でなければ書けないというタイプの昆虫記です。熱帯ではおしっこに蝶々(ちょうちょう)が集まるという話など、ビックリですよ。  学研漫画 日本の歴史全16巻 学習研究社 (1982)
学研漫画 日本の歴史全16巻 学習研究社 (1982)読書通信3度目の漫画の紹介です。私は漫画は後回しにするたちの大人ですが、これは積極的にお薦めします。中学卒業まで一度は見ておくといいですよ。おもしろくてためになること請け合います。歴史がきっと好きになりますよ。  さわわれたデービッド R・L・スティーブンソン作 坂井晴彦訳 (1886→1972)
さわわれたデービッド R・L・スティーブンソン作 坂井晴彦訳 (1886→1972)この本の著者はあの『宝島』を書いた人です。この本は有名ではありませんが、おもしろさは抜群です。主人公デービッドは実のおじにだまされて、奴隷にされかかります。船での戦闘、船の沈没、小島からの救出、その後の追っ手からの逃げ延び、最後のおじとの対決まで、息もつかせずに一息に読めます。  ともしびをかかげて ローズマリ・サトクリフ作 猪熊葉子訳 (1959→1969)
ともしびをかかげて ローズマリ・サトクリフ作 猪熊葉子訳 (1959→1969)私が大好きな、大好きなイギリスの小説家、サトクリフの歴史小説の1つです。アクイラというほこり高き若者が、自分の家族を殺した侵略者達の軍に、指揮官として20年後に大勝利を収めるという話にからませて、家族のこと、友情のこと、ふるさとのこと、そして人は何のために生きるかということを問いかけます。
  読書通信「アトレーユ」 28号 読書通信「アトレーユ」 28号 はれときどきぶた 矢玉四郎 (1980)
はれときどきぶた 矢玉四郎 (1980)母さんがぼくの日記をこっそり見る!これは深刻は問題だ!そこで「いっそメチャクチャなことを日記に書いてやれ」といろいとなでたらめを書くのだけれど、困ったことにその通りにどんどんなっていってしまう・・・  ぼくらのジャングル街 J・R・タウンゼント作 亀山龍樹訳 (1961→1976)
ぼくらのジャングル街 J・R・タウンゼント作 亀山龍樹訳 (1961→1976)主人公ケビン13才、妹サンドラ12才。両親に死に別れ、たよりないおじさん家族と住んでいたが、そのおじさんが家出した!離ればなれになりたくないケビンたちは幼いいとこたちを連れて、原っぱの空き倉庫のかくれ家で自活し出すが、そこは何と・・・  三銃士 アレクサンドル・デュマ作 朝倉剛訳 (1844→1977~78)
三銃士 アレクサンドル・デュマ作 朝倉剛訳 (1844→1977~78)1625年、フランス、青年ダルタニャンとその仲間アトス、ポルトス、アラミスの三銃士の冒険物語。パリに着くやいなやダルタニャンは三人の銃士と12時、1時、2時とたて続けに決闘をするはめに陥ってしまう。一度負ければすなわち死なのだからたまらない(そこで死ぬわけはないけれど)・・・読まなきゃ損するおもしろさ!  ドクトルマンボウ航海記 北杜夫 (1960)
ドクトルマンボウ航海記 北杜夫 (1960)著者、北杜夫が若き日、水産庁漁業調査船照葉丸610トンに船医として乗り込んだ半年にわたる体験記です。著者と船乗りたちの日常雑記が、今読んでも予想外に新鮮でいいのです。著者は医者は医者でも精神科が専門。学生時代から以後、メスをにぎっていない。地中海航海中に、甲板次長がどうやら盲腸(もうちょう)になった・・・
  読書通信「アトレーユ」 29号 読書通信「アトレーユ」 29号 日本(めぐるきせつかわるけしき) 岡部牧夫 文 たかはしきよし 絵 (1987)
日本(めぐるきせつかわるけしき) 岡部牧夫 文 たかはしきよし 絵 (1987)沖縄の名護・広島の久井町、三重の尾鷲、石川の白峰村、千葉の船橋、北海道の斜里町の5つの場所を全国から選んで、4月・7月・10月・2月のそれぞれの四季の風景を美しく、それでいて正確さを失わずに描いた絵本です。心が洗われる気がします。  三太物語(さんたものがたり) 青木茂 (1951)
三太物語(さんたものがたり) 青木茂 (1951)舞台は相模湖のそば、時代は戦争が終わってまもなく、三太が川でおぼれる!大うなぎをつかまえる!ハチの子を食べようとしてハチにさされる!村長の家のかきをとりに行って一人だけつかまってしまう!真夜中の湖水上で女の歌声が聞こえる・・・  ぼくはコック長 木沢武男 (1987)
ぼくはコック長 木沢武男 (1987)14才で家を飛び出し(木沢さんは、どうしようもなかったんだ。まねするなよ!)、街のお汁粉屋兼洋食屋の住み込みを振り出しに、19才で東洋ホテルの料理長、今ではプリンスホテルの総料理長となった名コックさんの興味深いホテルの台所の話、料理のこつの話、ぞっとする話、名コックになるにはどうすればいいかの話など。  バーナード・リーチの日時計 C・W・ニコル作 松田銑(せん)訳 (1982)
バーナード・リーチの日時計 C・W・ニコル作 松田銑(せん)訳 (1982)ニコルさんはテレビに出たりもしているので知っている人もいるでしょう。この本は「日本刀」-いち外国人の日本観。「バーナード・リーチの日時計」-人の生きる意味。「エチオピアの王先生」-動物保護。「わが心のクリスマス」-教育について。などひさしぶりに「かなわないなー」と思うほどスケールの大きい本格随筆ばかりです!
  読書通信「アトレーユ」 30号 読書通信「アトレーユ」 30号 黒つちがもえた 大竹三郎 (1974)
黒つちがもえた 大竹三郎 (1974)黒つちがもえる?もえた後の土の色?微生物の体から、土がかたまるのりの液が出ている?ミミズのふんが栄養になる?(これは聞いたことがあるぞ)という調子で大竹さんのおもしろい考え方で身近の話がとてもおもしろくなってきますよ。  鳥の島漂流記 谷真介 (1980)
鳥の島漂流記 谷真介 (1980)船乗り長平が4人の仲間と必死の漂流の結果、名も知れない大鳥しかいない絶海の無人島に漂着した。しかし、仲間は次々と死に、長平一人が残る。やがて後から流れ着いた二組の船乗りたちと力をあわせ、12年かけて島を脱出する。江戸時代の感動的な実話。  ぼくの先生はカバだった 西山登志雄 (1984)
ぼくの先生はカバだった 西山登志雄 (1984)東武動物公園園長の伝記。16才で上野動物園に就職できたはいいが、一年間人間様の便所掃除ばかりだったという話がまず感動的。20才のときの新聞記事企画でりっぱな発言をした若者に交じってボツ原稿寸前で著者の記事もでたが、それから何十年かして調べたら、元の職場でがんばっていたのは彼だけだったという話もいいな!  スプレー号世界周航記
スプレー号世界周航記キャプテン・ジョシュア・スローカム作 高橋泰邦訳 (1900→1977) 1895年4月から1898年6月までかけてヨットで世界で初めて一人で世界一週したスローカムの手記。今でも大変なこととして新聞に載るぐらいですから。ましてこのおろの大変さはdのおなものだったか。そして、kそういう快挙を抜きにしてもこの手記はいいですよ。何よりスローカムの人柄がいいのです。マゼラン海峡を通過する話は手に汗をにぎりました!
(c) 2004-2014 必ず役に立つ体験記
|