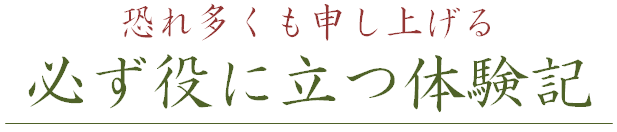|
漢検準1級合格体験記
〈試験編〉
 テスト内容 テスト内容各分野に考慮しておくといい特徴があります。ここはもっと分析した方がいいのですが・・・
 ①前半-音読み/後半-訓読み ①前半-音読み/後半-訓読み前半をよくしくじります。この学習を始めた頃、前半の読みが音読みと制限されていることを知らず、「蜘蛛」の解答が「チシュ」とあって、さすがに「きれ」ました。今でも問題だからがまんして解答しますが、「蜘蛛」は、「くも」でしょう!
 ②常用漢字の表外読み ②常用漢字の表外読み前後関係から憶測して、結構わかります。
 ③熟語-訓読み ③熟語-訓読み類推は効きにくい。知らなければまず読めません。びっくりの読みが多いです。
 ④常用漢字化 ④常用漢字化まちがえてはいけないところ。私もまあまあです。
 ⑤誤字訂正 ⑤誤字訂正ここは本当の実力がばれるところです。私はここをよく落とします。なぜだかもちろんわかりますよね!
 ⑥四字熟語とその語義 ⑥四字熟語とその語義準1級配当漢字を含む四字熟語は案外限られているせいで、学習して点が稼げます。私も途中から結構できるようになりました。
 ⑦一般の書取 ⑦一般の書取勉強すべきところ。ひたすら書くことです。同じ問題がよく出題されます。
 ⑧対義語・類義語 ⑧対義語・類義語対義語は反射的には出て来ません。見て、反対を考え、書くということになり、一工程多くなるせいで、疲れるのです。練習中、時間ばかりかかり、いやなところでした。
 ⑨故事・成語・諺 ⑨故事・成語・諺⑦と同様ひたすら書く。同じ問題がよく出ます。
 ⑩文章中の読みと書取 ⑩文章中の読みと書取あきらめずにやるしかありません。この分野はやり始めたころは0点に近くなりそうな恐怖感すら覚えました。最近は「ここは6~7割とれればいい」 「何とかなる」と自己暗示をかけて解いていました。満点は取れないとたかをくくって やればけっこう何とかなると思います。
 受験経過・作戦 目標は8割取ること。いつか必ず受かる! 受験経過・作戦 目標は8割取ること。いつか必ず受かる!予想より準備は容易 一旦この世界に入りさえすれば、予想よりはるかに準備しやすいと感じています。純粋に記憶力の勝負。何よりありがたいのは、出やすい漢字とまず出たことがない漢字があることです。2回目の受験直前にインターネットで「漢検準1級3ヶ月攻略法」サイトを見つけました。とてもいいサイトで、こういう情報がインターネットの利点と感心。管理人さんによると「最新の過去問を過去9回分完璧にマスターすると準1級に『ほぼ』合格します」とのこと。私は今年の試験分をいれても7回分しか持っていませんが、その発言は分かる気がしました。確かに主要部分が繰り返されています。いい例として、ここは危ないから見直しておこうと思った漢字が1回目も2回目も結構出ていました(憂鬱、・親戚の戚や渉外の渉・山葵・箆・轡)。
1回目は合格まで14点 最初の2003年第一回の挑戦のときは一切欲をかかず、①の一番薄い早稲田教育出版の本と②の厚い繰り返しの本を見るのみの2ヶ月でした。それで146点、合格まで後14点でした。受験直後の自己採点のときは減点法で158点まで確認してこりゃだめだと後はもう見ませんでした。結果との差でどうも納得できないところを何度も見ていたら自分が白という字の点を妙な書き方をするくせがあることに気がつきました。もしそれが原因なら6点分納得。それにしても、後から考えると、これは手探りの受験にしてはいい線を行っていたのだと思うのです。むしろ取りすぎぐらいに点が取れたと考えるべきでしょう。学習するときに基本書をしぼるのはあらゆる受験に共通でした。
欲ばった対策から撤退 秋の2度目対策は、最初は欲ばって準1級配当1017字対応の③の本から始めましたが、これは見事に失敗しました。最初の1ヶ月がんばりましたが、1017字を約50回に分割しているので、1回1回通読するだけでもう大変でした。この年にして初めて知る「よなげる(淘)」「ほとびる(潤びる)」などの日本語の動詞までいくつもありました。さらに、おおかたの常用漢字の表外の訓読に手こずりました。常用漢字の表外読みは準1級の他の分野に比べて労多く効少ない。あっさり言えば先の例の「胡」を使い分けるのは私には「無理」です。この調子では進めたとして繰り返すための時間が取れなくなると判断し、撤退。夏の繁忙期終わった9月からまずもう一度①②をしました。これはよかったです。ひょっとしたら作戦はこれに尽きているのかもしれません。
予想問題と過去問を解く その後③の代わりに予想問題風にしてある④と⑤の本を2冊で26回分、その他で13回分、計39回テスト形式(漢検13年分)で確認。とはいえ、これは結局のところ「確認」ではなく、学習する度に新たに知らない漢字が次々と出て覚えるのにまた結構時間がかかったというのが真相。それでもこの形式だと自分の現状がわかり、あきがなく、しかも一回分を1日で仕上げようと考えるので無理も効き、怠けようとする気持ちをある程度おさえられ、良かったです。一回分は「テスト、丸付け、間違い見直し、再テスト、再見直し、納得」の工程を一巡してアッという間に一日(最低でも1時間半)が終わります。やっていてだいたい140~160点でした。一方過去問を解いてみると、いずれも合格最低点の160点を越していたので、こういう予想本の常で、本番はこれより易しいと確信しました。よくても悪くても今の実力を維持する作戦にしました。
直前は基本の確認 後2週となった時点で新しいことをするのをやめ、基本の確認のため、最初の①と②の2冊にまた戻りました。最終的に①は6回繰り返したことになりますが、6回目でも学ぶことはありました。②はボリュームがありすぎ繰り返しの3度目は結局全部は出来ず、やや中途半端なうちに秋の本試験の10月26日(日)。
 暗記あれこれ 「読み」と「書き」は別試験と考えるべき 暗記あれこれ 「読み」と「書き」は別試験と考えるべき結局どれも出題漢字のことを真剣に考え、不正確な記憶であることを自覚し、練習すれば、段階的に深い記憶になっていくわけです。そんなことは皆様にはとっくにご承知のことと思いますが、覚えるまでの間におきた現象のいろいろが妙におもしろく、しなくてもいい分類をしてみました。
漢検は、誰に聞いてもある級になると皆一様に「読めるが書けない」と言い出します。「書けるが読めない」と言われる方にはおめにかかったことがありません。人の名と顔の記憶が一致しないのがいい例だと思いますが、脳の記憶場所が違うのでしょう。「読み取り」を「人の顔」に、「書き取り」を「人の名」にたとえるとよくわかるのではないでしょうか。
 読み取り 読み取り年の功で結構健闘しましたが、後一息が難しい! 健闘したととりあえず言ってはみましたが、何度も書きましたように「常用漢字の表外読み」は前後関係、文脈からの類推がきかないことが多くて困りました。読書体験はある程度ものをいいましたが、今の新書、文庫から専門書までをいくら読んでいても無理がある気がしました。例えば私が大学生のときに買った福沢諭吉の「学問のすゝめ」はこの表外読みだらけでしたが、何年か前に本屋で見たときはもうひらがなに直してありました。したがって身近に機会はなくなったわけです。大学の文学部国文科あたりにいかなければ日常にはそもそも接しません。読書派もこの辺りが限界になります。
 書き取り 書き取り私ももちろんこちらがだめでした。準1級配当の漢字は常用漢字+1017字ですから社会人にとっては見たこともない漢字はおそらくありません。その中で「最初から出ない」というのは一番だめな状態でしょう。これはそもそも知らないからです。
「ど忘れ」と一瞬思うのが次。本当に「ど忘れ」の場合もあるでしょうが、意識の錯覚で、読めるから頭の中にほんの一瞬「絵」として浮かぶのでしょう。それをさして「ど忘れ」と考えるのだと思うのです。後で答えを見て、「読めるんだがなー」と私はもちろん、周りの皆もよくくやしがります。実はその漢字に対する脳の中の書く分野をまだ使っていないということではないでしょうか。
その次あたりに、「書けるつもりだが細部がはっきりしない」という漢字がずいぶんあります。扁や旁(つくり)の片方がぼけることが多いのです。旁はたいてい「るまた」、「のぶん」などに収斂。おそらく「るまた」、「のぶん」等、本来の出自を知らないで単なる記号として認識しているからぼけるのだと思います。この3番目の状態ともなるともう一息で書けそうなので、答案の余白にいくつもいくつも試し書きすることになります。もっともそれで合う確率は、経験ではせいぜい5分の1ぐらいです。極め付きは秋の試験で出た「轡」です。糸も車も口もすべて思い出してそれらが全部違う位置で漢字を創ってしまいました。帰宅後思い出して驚いたの何の!試験対策用の記憶の底の浅さが見事露呈しました。そういえば他にも「葡萄」や「麒麟」などの字も勢いで当初は書けていたのですが、しばらくするとぼけてしまって覚え直しをしました。勢いで覚えたということは、きっと視覚に訴えたからなのでしょうね。
一番最後のよくある例は、その漢字に「´」があったかなかったかの点検(旺、奄、痕、稽、蔑、拭、葡・・・)。これは常用漢字化の過程でも点を削除したりしているのだから困ります。「そうか、「´」があるかないかが大問題だ!」と気がついて意識し出しました。ここらを意識し出す頃合格点に近づいて来るのでしょう。「´」とは逆に画数の多い装飾系の文字、例えば、祈濤の濤や敏捷の捷、簾、素麺の麺なども記憶しにくい。
話が少しずれますが、「臼・蠅・鼎・麺・繍・・・」の筆順がまったくわかりません。何を見ても筆順は書いてないのです。結果、幼稚園生と同じように「字」ではなく「絵」として書いています。「蠅」という字など書きながらサザエさんに出てくるカツオ君の姿が浮かびます。友達の答案を逆さに書いて頭を掻いているのと全く同じで、「お絵かき」です。本番で出たものはもちろん略字で済ませました。おもしろいことに、何度も意識して書いたので却って覚えてしまいました。
 問題集使用頻度と模擬テストの得点状況 問題集使用頻度と模擬テストの得点状況こういう情報こそが役にたつと思います! 「この記録ぐらいは抜いてやる」と思えばはかどります。
 試験当日 試験当日予想より受験者が少ない!
(会場発表)
会場は取手の関東理工専門学校。午後3:30~4:30。前回は受験者19名でしたが、今回はさらに少なく11名。ちなみに1級受験者はたったの2名。圧倒的に多いのは2級で79名。次が準2級63名。今回も見回すと私が最年長。6級受験のかわいらしい小学生達と同教室でした。うっかり携帯の時計しか持ってこず、今回初めて教室に時計がなかったため、少し困りました。幸い試験官が何度も時刻を言う人だったので何とか間に合いました。
1の読みは順調。感触よく始まりました。始まって30分で8番の途中対義語の最後まで。終わるのに40分はかかります。見直しというか、気になるところのチェックでアッという間に後4分。さすがにそこですることがなくなりました。終わった時点では受かったと思いこみ、家族に「受かった」と宣言。しかし、会場でもらった模範解答で自己採点すると意外にぼろぼろと・・・またぼろぼろと・・・
(c) 2004-2014 必ず役に立つ体験記
|