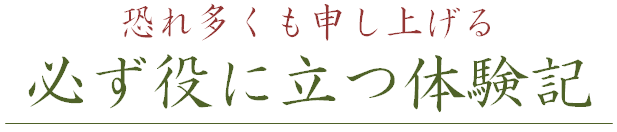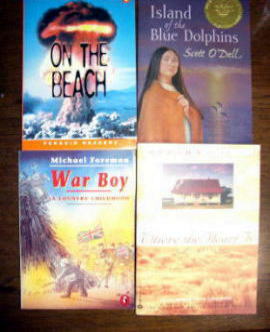英検準1級合格体験記
〈後編 英検準1級からの道 1〉
 英語に関する勉強はもうたくさん!
英語に関する勉強はもうたくさん!英検準1級に何とか受かり、「英語に
関する勉強はもうたくさん」と思い、目標を「英語そのもの」に切り替えました
(1)。
(1) 思えば不思議な話です。私がそうですが、英検の上級やTOEICなどに挑戦し始めると、できるだけ英語の原文に触れようと心がけるのですが、それでも接する本は2次加工されたものが多い。勉強臭は薄まってきますが、まだ日本語を介した英文でしかありません。いつまでこんなことを続けているのでしょうか・・・英語病と言われるゆえんです。一方NHKの放送とテキストにつきあうだけでも今やすごいことになってきています。一種の英語のバーチャルリアリティー世界です。(ひょっとするとNHKテキストでアメリカ人も学習しかねない?私はよくNHKの教育チャンネルの日本語講座見ますしね。)あまりによくできているのでこのシステムを輸出してはいかがかとすら思います。
 初めはハリーポッターからでした 音聴とタイアップ
初めはハリーポッターからでした 音聴とタイアップ合格前後、音読と音聴に凝っていたせいでハリポタのカセットを知りました。あわせて書店で英語勉強コーナーに平積みされ始めていたハリポタシリーズも見、どちらかと言うと音への興味からカセット購入というちょっと高い買い物をしました
(1)。最初は専ら、カセットを散歩の友としました。これが意外や、朗読者 Stephen Fry さんがいい声で、聞き手をわかる気にさせてくれました
(2)。
カセットは何巻にも分かれていたせいで、先にカセットで表裏60分前後の朗読を聞き、終えるごとにそこまでの範囲を本で読みました。冒頭のページから知らない単語だらけでひるみました。辞書を引かずに進むと決めていましたが、現実の前にはいかんともしがたく、一度ストップし冒頭に戻りました。意外に難しい単語が続出しているのです。「ハリポタなど子供の話」と最初は斜めに構えていただけに予想外でした。しかし、ありがたいことに話は面白く、カセット→本→カセット→(繰り返し)とうまい具合に進み、気がつくと20日間で読了しました。
最も、読了するまで一方で「とてもじゃないが終わらないだろう」とも思い続けてもいました。「この本終わるかなー」と思うこのくせは今も残っています。それだけに、いやーうれしかったです。何度も何度も本をパラパラめくったりしたものです。何しろ326ページもあるのです。
しかもハリポタシリーズを当初は斜めに見て、興味を持たなかったため、すでにハリポタは2巻・3巻までペーパーバック化されていたのが幸いでした。書店で次の2のカセット集を買うか買わないか何度も迷ってコーナーの周りをうろうろしたことを未だに覚えています。私にとってそれほどにも高い買い物でしたが、勢いで2巻・3巻とカセットごと購入しました。
結果、本とカセットの相乗効果で一気に2ヶ月ほどで3巻まで終了。いやー、おもしろかった。さらに当時とんでもない天文学的ページ数と思っていた800ページ近い4巻も話につられてカセット付きで仕上げ、すっかり「英書読めます」気分を味わったものです。最も、そうは問屋が卸さないことは後で知りました。苦労の始まりでした。
(1) 後に5、6は予約してハードカバーで読みました(さすがにカセット5・6は未購入。店頭では今やCDしか見かけませんね)。それにしても、ハリポタで使っている単語は子供向けではないと感じます。ハリーポッターの連作のいいところは予想もしない舞台設定(クィディッチ一つとってもこの発明はすごい)のすばらしさ。一方、ハリーの性格設定についていけない人も多いと思われます。「なぜそこで向こう見ずに進むんだー」と私も何度本に向かって叫んだことやら・・・きっと毀誉褒貶いろいろでしょうが、私はこのシリーズをはらはらどきどき系の大作としてぜひ薦めたいです。
(2) 音聴は朗読者にもよりますねー。ハリポタの Stephen さんはすばらしい。さらに言うと音聴の素材は Unabridged(無削除)版 が絶対お薦め。とはいえ、Unabridged は費用もかかるし、そもそも版元が大ヒット本以外出すわけがありません。そこが難しい。結局ハリポタ以外余りいいなと感じたものがないのが私の実情です。とはいえ、音聴は私は別ジャンルとして期待していますので、いつか再開したいと思います。ちょうどテレビや映画に対してのラジオの存在価値と似ていますね。
 児童書は宝の山 皆さんがおっしゃっている通り、大人も楽しい。本当ですね!
児童書は宝の山 皆さんがおっしゃっている通り、大人も楽しい。本当ですね!並行してパフィンシリーズを中心とした児童書を読みました。児童書は読書の貴重な宝庫です。トムの真夜中の庭、赤毛のアン、宝島、あしながおじさん、小公子、ハイジ等大いに楽しめました。人には言いにくいですが、このころは自分の中ではあまりのおもしろさに、大げさですが忘我の境地でした。その上ルイス・サッカーの「穴」やカニグズバーグの作品群など、現代の傑作にも数々遭遇し、まるで子供時代のように夢中で読みました。約40冊ほどです
(1)。
今でも児童書は人に勧めたりしています。それでも、オルコットの「若草物語(Little Women)」や、ウィスの「スイスのロビンソン」のような私にとっては今ひとつのものが次第に混ざり始めました。さらにシャーロックホームズの冒険物は単語のみならず読み取りも難しいことに気がつきました。大人用だったのですね。手に入れたパフィンブックスの残りは続編が多く、一作者一作としたせいもあり、児童書からそろそろ一度卒業することにしました。
(1) 読んだ児童書 The Little Prince /Alice's Adventure in Wonderland /Charie And The Chocolate Factory /Charlotte's Web /The Story Of Doctor Dolittle /Tom's Midnight Garden /From The Mixed -up Files Of Mrs.Basil E Frankweiler /Stuart Little /Where Were You, Robert /Daddy-Long-Legs /Anne of Green Gables /A Little Princess /Encyclopedia Brown 18 /Heidi /Little Load Fountleroy /Treasure Island /The Family From One End Street /Little Women /Robinson Crusoe /The Great Adventures of Sharlock Holmes /The Extraordinary Cases Of Sharlock Holmes /The Mysterious Adventures of Sharlock Holmes /About The B'nai Bagles /Journey To an 800 Number /There's A Boy In The Girl's Bath Room /Jennifer ,and Me ,Elizabeth /Around The World In Eighty Days /Island Of The Blue Dolphins /Dogs Don't Tell Jokes /Rocket Ship Gallileo /The Adventure of Tom Sawyer /Mary Poppins /The Swiss Family Robinson /Emil And The Detectives /War Boy /Holes/Sarah,Plain and Tall /Bread Winner /The Great Brain Does It Again /A Bear Called Paddington /The Machine Gunners /The Bad Beginning /Seedfolks /Madame Doubtfire /The Curious Incident of The Dog In The Night-time / The View From Saturday / ・・・47
その中での特筆ものの本 Michael Foreman「War Boy」/Scott O'Dell「Island of the Blue Dolphins」/Louis Sacher「Holes」/Stevenson「Treasure Island」
 多読用の単語制限本
多読用の単語制限本酒井邦秀さん・伊藤サムさんの 英書読もう運動(多読・やさたく)に参加してみました。
- 酒井邦秀さんの「快読100万語ペーパーバックへの道(2002)」
- 伊藤サムさんの「やさしくたくさん、身長の2倍(「英文記事の読み方」2000)」
ここらで「どうして英語が使えない(1993)」からすでに注目していた酒井邦秀さんの「快読100万語ペーパーバックへの道(2002)」と伊藤サムさんの「やさしくたくさん、身長の2倍(「英文記事の読み方」2000)」運動に感ずるものがあり、多読用の単語制限本をしばらく読み続けました。
酒井さんの始めた多読の勧めは、「教室で教える」という作業になじみません。それだけ大学での立場としても難しかったことが著書に記されていましたが、まったくその通りだと思います。自己学習しかありえない分野に集団授業従事者が分け入ったことは本当に尊敬に値します。私はこの方法が大学での英語学習の本流になることをせつに祈っています。伊藤サムさんのおっしゃること(やさたく)はそこに重なってプロになる道をさりげなく示しています。とは言え、この「身長の2倍」がくせもので、言うは易しいが、これは本当に大変です。この後編もその大変さを言いたいのが半分です。
初めのうちはものめずらしさと初期馬鹿力でどんどん進みました。多読用の単語制限本も普及のおかげでジャンルの幅ができ、しかも量がはける。夢中になっているうちに「100万語」は達成できます。しかし、・・・
あるとき 本物がそうとうやさしいせいなのですが、本物のThe Street Lawyer を読み始め、以前に読んだ同書の単語制限本と比べたときに愕然としました。読後の充実感がまるで違うのです。そりゃーわかるのなら本物の方がいい。単語制限本の限界をここで感じてしまいました。限界であって無意味なのではまったくありません。どの方の場合もこういうエピソードがきっかけになって次の段階に移行していくのでしょう。私もこのとき単語制限本はそろそろ一回卒業しようと思いました。ここまで約20冊
(1)。
(1) 読んだ多読用の単語制限本 Cranford /The Street Lawyer /Death In The Dojo /The Firm /A Tale Of Two Cities /I Rovot /On The Beach /East 43rd Street /Captain Corelli's Mandolin /The Body /When Summer Comes /The Go-between /The Silver Sword /The Death of Jericho /Do Androids Dream Of Electric Sheep? /Wuthering Heights /Remains Of The Day /The Grapes Of Wrath /The Amsterdam Connection /Fly Away Home /The Full Monty /Godwulf Manuscript 22
拾い物な気がした本
| Elizabeth Gaskell |
Cranford |
オクスフォード4 |
| Ian Serraiccier |
The Silver Sword |
オクスフォード4 |
| Nevil Shute |
On The Beach |
ペンギン4 |
| Stephen King |
The Body |
ペンギン5 |
| Louis de Bernieres |
Captain Corelli's Mandolin |
ペンギン6 |
| Frederick Forsyth |
The Day Of The Jackal |
ペンギン4 |
「快読100万語」の寸評と違い、Elizabeth Gaskellはおもしろかったです。
後ろの5冊はこの長さで十分楽しめます。
 丸善で首が痛くなりました!
丸善で首が痛くなりました!一般英書の棚をときどき日本橋「丸善」、新宿「紀伊国屋」、神田「三省堂」、池袋「ジュンク堂」などで見始めました
(1)。英書コーナーを訪れることそのものがうれしいという時期。ずばりミーハー期ですね。あるときの丸善でのことを思い出します。何しろそのころまでの私は現代ものの翻訳文学というか、エンターテインメント小説に何の興味もなく人生をすごして来ています。棚を見てもどれがどれやらさっぱりわかりません。悲しいかな、せいぜいジェフリー・アーチャー、シドニー・シェルダンとダニエル・ステーィルぐらいです。それも名を知っているだけで読んだわけではありません。そもそも英文の表紙をどう効率よく眺めるのかもわからず、横に書いてある表紙を眺めるので首が痛くなってしまいました。そりゃーそうです、2時間から首を斜めにして眺めていたのですから。
(1) それぞれの本屋にはそれぞれの味があります。並べ方一つでも主張になっている。 通い始めると違いが気になります。同じ書店でも久しぶりに行くと変わっていたりする。最近は店員さんのお薦めを必ずチェックします。気が利いていることが本当に多く、よく購入します。それで得した気がするのがWhere The Heart Is/The Seed Folks/前出のWar Boy/Island Of The Blue Dolphines などです。書店員さん、がんばって下さい。見ていますよ。新宿南口、紀伊国屋、オアゾ丸善最近いいですねー。
 大衆小説(エンターテインメント)と推理小説に挑戦
大衆小説(エンターテインメント)と推理小説に挑戦それでもためしに買った、パトリシア・コーンウェルの Postmortem。 友人の高校の英語の先生が読んでいると言っていたのを思いだし、「本当かよー」というぐらいの疑わしい気持ちで買ったのです。すると、もちろんちょっとした対抗意識で気合いをこめて読み始めたのですが、読めました。うれしかったですねー。ハリポタとは違う、大人の本が読めた感動です。伏線も何もない○○が突然出るのには正直ガッカリしましたが、そういう作品への評価は別として、読めたことが何よりでした。
さらにまた、大流行中のダン・ブラウンのDa Vinci Code(2003)の平積みの山を目にして、「流行中の本の原書がここにあるけれど、読めるんだろうか?」「どうして読もうとしないの?」と、まるで関係ない世界のように感じていた世の中の流行と自分とが一瞬にして線でつながり、購入し、ためしました。するとこれまた内容の余りのおもしろさに一気に読めました。と言っても睡眠時間を削ったりしながら15日間かかりました。家人が先に翻訳を読んでおり、からかわれたりしながらの迫害に耐えてだったことを言い添えておきます。
 英書リスト本の利用 私は今「洋販」王国の住民です
英書リスト本の利用 私は今「洋販」王国の住民です 「ミステリーで英語漬け(1997)」
「ミステリーで英語漬け(1997)」この時期、多読用単語制限本のリスト以外の手に入る英書推薦リスト本は2つしかなく、私は日本語では推理小説もまず読まないたちなので、エンタメに続いて推理小説というジャンルにもどうにも抵抗がありましたが、次の目標として「ミステリーで英語漬け(1997)」の巻末リストに挙げてある本を読み始めました。私、何しろ87分署シリーズや、スペンサーシリーズ、ハードボイルドなどの、ミステリー基本用語にすらまったく疎い。それでもさすがの出口さんの選書力、 The Key To Midnight のような落ちが○○○になる話や、レッドドラゴンのようなサイコパス系には辟易しましたが、このリストは本当にしっかりしていて、大いに役にたちました。20冊ほど読破
(1)。
(1) 読んだミステリー小説 For Kicks / Odds Against / Eight Million Ways To Die /The Bone Collector /The Sculptress /Congo /Early Autumn /Cop Hater / In Cold Blood / A is for Alibi / The Dogs War /The Street Lawyer /The Godwulf Manuscript /The Key To Midnight /A Matter of Honor /Snow Falling On Ceders /Postmortem /Gone South /Red Dragon /And Then There Were None /Booked to Die / The Other Side Of The Midnight /Master Of The Game / ・・・ 23
 「洋書ハンターズ(1997)」
「洋書ハンターズ(1997)」もう一つのバベルプレスから出ている「洋書ハンターズ(1997)」はリスト集としてはなじめませんでした。抑えようとしたようですが、執筆者の好みが時にあやしい方にずれ、明らかにマイナーな選択になりすぎです。本当に残念ながら、今でもときどき見るのですが、余り利用していません。
 ワケありのペーパーバック300選(2005)」
ワケありのペーパーバック300選(2005)」そうこうするうちに「ワケありのペーパーバック300選(2005)」が洋販から出版されました。これは時期を得た出版。「まってました!」でした。家人の白い目を無視し、しばらく夢中で買いあさりました。短期間だとけっこうお金がかかるものです。1000円なら納得ですが時に2000円を超えるペーパーバックがあるのには閉口します。納得しにくい価格です。品切れなのか、なかなかお目にかかれない本や、表紙が実物ではどうなのかなどという興味も手伝い、しばらく楽しく1〜2年過ごしました。こういう、初心者にとって楽しい時期はいいですねー。何の趣味にも共通の急接近期です。最近は、近くの大型本屋などではこの300選にのみ沿った品揃えにすらなってきました
(1)。
(1) 300選から(既出と重ならないもののみ) Animal Farm /Who Moved My Cheese /The Old Man And The Sea /Flowers For Algernon /A Walk To Remember /The Bridges Of Madison Country /Tears of The Giraffe /Forrest Gump /About A Boy /The Spy Who Came From The Cold /Tuesday With Morrie /The Twelfth Engels /The Sisterhood Of The Traveling Pants / Not APenny More Not A Penny Less / Dave Barry Does Japan / ・・・15
その他から Riding in Cars With Boys / Death Of a Salesman / The Christmas Boxes / Balzac And THe Little Chinese Seamstless / Love And Glory / THe House On Mango Street / Mackenzie's Mountain / Wenny Has Wings / Ben Franklin /
(c) 2004-2014 必ず役に立つ体験記
 英語に関する勉強はもうたくさん!
英語に関する勉強はもうたくさん! 初めはハリーポッターからでした 音聴とタイアップ
初めはハリーポッターからでした 音聴とタイアップ 児童書は宝の山 皆さんがおっしゃっている通り、大人も楽しい。本当ですね!
児童書は宝の山 皆さんがおっしゃっている通り、大人も楽しい。本当ですね! 多読用の単語制限本
多読用の単語制限本 丸善で首が痛くなりました!
丸善で首が痛くなりました! 大衆小説(エンターテインメント)と推理小説に挑戦
大衆小説(エンターテインメント)と推理小説に挑戦 英書リスト本の利用 私は今「洋販」王国の住民です
英書リスト本の利用 私は今「洋販」王国の住民です 「ミステリーで英語漬け(1997)」
「ミステリーで英語漬け(1997)」 「洋書ハンターズ(1997)」
「洋書ハンターズ(1997)」 ワケありのペーパーバック300選(2005)」
ワケありのペーパーバック300選(2005)」