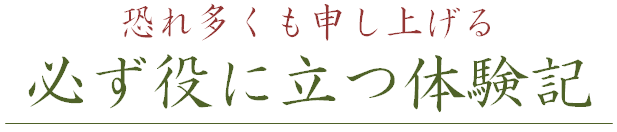|
鉄板の面白さ!「児童書300選」
〈その3〉
 読書通信「アトレーユ」 31号 読書通信「アトレーユ」 31号 絵のなかを旅する
絵のなかを旅するS・ラファレール、C・メルロ・ポンティ、A・タルディ編著 大西昌子、広訳 (1980→1987) 表紙の絵を見て下さい。誰が書いた絵かわからないのですが、女の人のファッションや看板の字からいろいろななぞが解き明かされてきます。一枚の絵がいろいろなことを語っていることをわかりやすく教えてくれる絵本です。  ぼくおとなにまけないぞ 春風亭柳昇 (1987)
ぼくおとなにまけないぞ 春風亭柳昇 (1987)落語家、春風亭柳昇さんお子ども時代の伝記です。武蔵野の一角の農家がどんな日常生活を送っていたのか、柳昇少年がどう貧乏に負けないでがんばったか?私は同じ町内で子ども時代を過ごし、柳昇さんの親戚達と机を並べていた(もちろん戦後)ため、なつかしさは人一倍でした。  ゲド戦記 アーシュラ・ル・グイィン作 清水真砂子訳
ゲド戦記 アーシュラ・ル・グイィン作 清水真砂子訳
Ⅰ 影との戦い (1968→1976) Ⅱ こわれた腕輪 (1971→1976) Ⅲ さいはての島へ (1972→1977) 表紙を開くと作者が創り出したアースシーの世界の地図が広がる。魔法使いを志したゲドという若者が、ふとした若気の至りから禁じられた呪文を唱えてしまい、死の国の影をこの世に出してしまう。自らの命と世界の運命をになった死闘が始まる!  福翁自伝 福沢諭吉 (1899)
福翁自伝 福沢諭吉 (1899)福沢諭吉の口述筆記を元にした自伝です。緒方洪庵の適塾に学んだ時期と咸臨丸での太平洋横断が有名ですが、全編に流れる「合理の精神」には脱帽です。諸君、適塾や慶應義塾の勉強方法に学べ!ですね。中3にはやや難しいですが、現代に通じる自伝の一つです。
  読書通信「アトレーユ」 32号 読書通信「アトレーユ」 32号 たぬき学校 今井誉次郎 (1958)
たぬき学校 今井誉次郎 (1958)タヌキのポン太が漢字を百字書く宿題で、「松」という字を木木木木木・・・と書いてから公公公公公・・・と書いてすませたり、とうとう書いていかなかったりします。ポン先生がこれを知って、さてどうしたでしょうか?楽しいお話ですよ。  家出 12歳の夏 M・D・バウアー作 平賀悦子訳 (1976→1981)
家出 12歳の夏 M・D・バウアー作 平賀悦子訳 (1976→1981)主人公ステイシーは11歳の女の子。5歳で母が家を出て行き、父親と二人で暮らして来たが、最近バーバラという父の恋人が家に来た。ある日、そのつもりもなく家出するのだが、荒野を放浪し、犬に導かれて一人暮らしのエラばあさんの家につく・・・  西遊記 呉承恩 作 君島久子 訳 (宋→元→明→清→1975~1976)
西遊記 呉承恩 作 君島久子 訳 (宋→元→明→清→1975~1976)たいていの諸君はこの話の筋はとっくにご存じのはず。三蔵法師、孫悟空、猪八戒、沙悟浄、そうそう、一飛び十万里のきん斗雲、重さ一万三千五百斤の如意金箍棒。どれも有名ですが、「弟子玄奘(ていしげんじょう)、ただいま参着」というまでに何と寒暑を十四度過ごし、八十の苦難に遭っていることのすべてを読みたい人にお勧め。  一筋の道 第一部・第二部 丸岡秀子 (1971、1975)
一筋の道 第一部・第二部 丸岡秀子 (1971、1975)舞台は長野県佐久盆地。主人公恵子は明治39年、生後9ヶ月で実母と死に別れ、その後祖父母に貧しい中、育てられていく。自分を引き取らない父への屈折した思いと、没落した庄屋の暮らしとが、幼い恵子の目を通して丁寧に綴られていきます。読んでいて主人公への熱い共感を抱かずにはいられません。余談ですが、中に主人公の受けた大正2年の女学校(今の中学受験)の入試問題があり、興味深いですよ。
  読書通信「アトレーユ」 33号 読書通信「アトレーユ」 33号 ごんぎつね 新美南吉 (1931~1942)
ごんぎつね 新美南吉 (1931~1942)『屁(へ)』という作品を教科書にのせることは残念ながら無理なようですが、それだけに、ぜひ読んでみてほしい!それにどの作品もなつかしい日本の昔のにおいがします。それでいて、どれも今のあなた方も「そうだ、そうだ」とうなずくものばかりです。  さすらいの孤児ラスムス リンドグレーン作 尾崎義訳 (1956→1965)
さすらいの孤児ラスムス リンドグレーン作 尾崎義訳 (1956→1965)孤児ラスムスが孤児院から逃げ出した。自分をもらってくれるやさしくきれいなお母さんを求めて。途中でオスカルという中年の風来坊と出会うが、二人して、銀行どろぼうとまちがえられる。しかも真犯人が誰かを知っているのはラスムスとオスカルだけ!さあ、どうなる?  とぶ船 H・ルイス作 石井桃子訳 (1936→1953)
とぶ船 H・ルイス作 石井桃子訳 (1936→1953)ピーターがいつもの角をまがると、あるはずのない通りがあった。歩いていくと店がある。そこで長さが20㎝もない小さな船を150円で買った。これが飛ぶ船だったのです。イギリスからエジプトまでひとっ飛び、時代までさかのぼれる。驚いたことに古代象形文字に自分のことが刻まれているのを発見する。そこでその時代に・・・  図説 日本の役所 榊原昭二編著 (1986?)
図説 日本の役所 榊原昭二編著 (1986?)1 国会 2 内閣 3最高裁判所 『公民』を勉強している中3にうってつけです。写真と図を多用していて、内容はかなり高度なのですが、あきずに楽しく読んでいけます。「おもしろメモ」という欄はときどき本当におもしろいことが書いてありますよ。教科書では触れない視点が満載!
  読書通信「アトレーユ」 34号 読書通信「アトレーユ」 34号 やぎと少年 アイザック・B・シンガー作 M・センダック絵 工藤幸雄訳 (1966→1979)
やぎと少年 アイザック・B・シンガー作 M・センダック絵 工藤幸雄訳 (1966→1979)7つの話はどれもすてきですが、私は、題にもなっている「やぎのズテラー」という作品が特に好きです。お金がなくてやぎを売りに出します。街に連れて行く途中雪が降り始め、道を見失います。やぎと少年はほし草の山の中に三日三晩とじこめられます・・・  極北の犬トヨン ニコライ・カラーシニコフ作 高杉一郎訳 (1950→1968)
極北の犬トヨン ニコライ・カラーシニコフ作 高杉一郎訳 (1950→1968)シベリアに流刑になった著者が旅の途中で記録した、犬のトヨン(だんな)とヤクート族のグランという誠実な男が、貧しい境遇から近隣の名士になるまでの心暖まる話。普通の物語の感覚よりも大自然の厳しさの分だけ詩情豊かな不思議な味わいがありますよ。  ひとり立ちへの旅 佐伯和子著 (1982)
ひとり立ちへの旅 佐伯和子著 (1982)佐伯さんは、普通に美術学校、美術大学で学ぶというコースを経ることなく、美容師、バーに勤務、イラストレーター、という職業を持ちながら、ほぼ独学で油絵を書き、途中から水墨画に転ずるというユニークな経歴の絵描きさん。思い立ってお金をかき集めてパリに行くところが特におもしろい。  図説 日本の役所 榊原昭二編著 (1986?)
図説 日本の役所 榊原昭二編著 (1986?)5 大蔵省 6通産省 8 外務省 12 農林水産省 前回に続いて『公民』を勉強している中3にうってつけです。この国がどんなしくみで動いているかを知るには絶好です。通産省の正式名称を言えますか?農林水産省は前は何省でした?(今は大蔵省は財務省・他に、通産省は、経済産業省(経産省)に変わりました。)
  読書通信「アトレーユ」 35号 読書通信「アトレーユ」 35号 さよなら おじいちゃん・・・・ぼくはそっといった
さよなら おじいちゃん・・・・ぼくはそっといったエルフィー・ドネリー作 神崎巌訳 (1977→1981) 主人公ミヒャエル・ニーデッキー両親、姉とおじいちゃんの5人暮らし、大好きなおじいちゃんが、がんにかかっている。両親の話をふと聞いてしまったニーデッキーはおじいちゃんに対するいろいろな思いがまざりつつ、おじいちゃんの死までの期間、人生を深く共有する。  おたずねものの犬ストーミー ジム・キュルガード作 前田美恵子訳 (?→1982)
おたずねものの犬ストーミー ジム・キュルガード作 前田美恵子訳 (?→1982)ひどい新飼い主に反抗してきずをおわせた犬ストーミーが、父がけんかで投獄され、一人留守の水鳥案内宿を守る少年アランに助けられる。吹雪の中の少年アランの沈着な行動に人間不信から立ち直る。一方アランは、父のいないさびれた宿の運命に心を砕くが・・・  T・N君の伝記 なだ いなだ (1976)
T・N君の伝記 なだ いなだ (1976)中学の歴史教科書にはたった一行しか説明されない『民約論』の訳者の伝記です。私はこの本を読むまで、当然この本は出版されていたとばかり思っていましたが、何とTN君の講義ののーとが人から人へと書き写されていって日本中にひろがって行ったのだそうです。歴史と教科書が歴史のすべてではないという絶好例。  図説 日本の役所 榊原昭二編著 (1986?)
図説 日本の役所 榊原昭二編著 (1986?)4 法務省・検察庁 7 文部省 9 運輸省・郵政省 10 建設省 11労働省・厚生省 この回で日本の役所シリーズは終了です。新聞やテレビでよく見聞きしている名前だけでなく、仕事内容が写真や図でよくわかります。(なお、今は文部省は文部科学省、運輸省・建設省は国土交通省、郵政省は総務省、労働省・厚生省は厚生労働省 に変わりました。)
  読書通信「アトレーユ」 36号 読書通信「アトレーユ」 36号 荒野にネコは生き抜いて G・D・グリフィス作 前田美恵子訳 (1973→1978)
荒野にネコは生き抜いて G・D・グリフィス作 前田美恵子訳 (1973→1978)この物語は「ネコが捨てられるとどうなるか」の一例の話です。読み始めると、主人公の子猫がけんめいに生き抜く姿に感動してしまいます。やがて自分の子どもが生まれるところなどうれしくなってしましますが、そこにもまたつらい運命が・・・  宝島 R・L・スティーブンソン作 坂井晴彦訳 (1883→1976)
宝島 R・L・スティーブンソン作 坂井晴彦訳 (1883→1976)宝は手に入ったと思いますか?私は話しのあらすじぐらいしっていると思っていましたが、読んでみると宿屋の部屋のところから知らなかったというおそまつ。しかし、ジョン・シルバーという悪漢はおもしろいねー!作者は『さらわれたデービッド』も書いているよ。  Treasure Island Rovert Louis Stevenson (1883)
Treasure Island Rovert Louis Stevenson (1883)私がそうでしたが、「宝島」のエピソードなど知っているようでほとんど覚えていないのではないでしょうか。人生に対する諦観とでもいう雰囲気のしめになるのが意外でした。実に新鮮でおもしろかったです。  ホビットの冒険 J・R・R・Sトールキン作 瀬田貞二訳 (1937→1951)
ホビットの冒険 J・R・R・Sトールキン作 瀬田貞二訳 (1937→1951)以前11号で紹介した『指輪物語』の序曲にあたる作品です。ホビット族のビルボ・バギンズというこびとが竜退治にでかけます。いやーおもしろかった!と思わず叫びたくなるほどおもしろい。まあ、だまされて荒れ地の国の地図を見てごらんなさい!君たちが夢中になっているテレビゲームのキャラクターの元祖なんだから。  ベル・リア シーラ・バンフォー作 中村妙子訳 (1978→?)
ベル・リア シーラ・バンフォー作 中村妙子訳 (1978→?)第二次世界大戦のただ中、占領直前のフランスの街道を行く旅芸人一座の犬。数奇な運命で生き残り、劣勢イギリスの駆逐艦ターシャン号のマスコットとなるが、飼い主に返すため、港におろされる。その夜、港町は空襲に会う・・・過酷な戦争下の人々を不思議な愛敬でむすびつけていく犬。読み終わると静かにテーマが聞こえてきそうな感動。
  読書通信「アトレーユ」 37号 読書通信「アトレーユ」 37号 父さんギツネバンザイ ロアルド・ダール作 田村隆一訳 (1970→1976)
父さんギツネバンザイ ロアルド・ダール作 田村隆一訳 (1970→1976)『チョコレート工場の秘密』で有名な著者の作品です。父さんギツネには家族が5人。ある日3人の農夫にシッポをうたれ、すみかのあなもほりおこされる。あと少しで殺されるという時にいい考えが浮かぶ!しかし、追いつめられて飢え死にしそうになる・・・  小公子(しょうこうし) バーネット作 吉田甲子太郎訳 (1886→1953)
小公子(しょうこうし) バーネット作 吉田甲子太郎訳 (1886→1953)今テレビでやっている作品の原作です。あんまり有名なのできちんとは読んでいない作品の良い例です。アメリカの少年セドリックがある日突然イギリスの伯爵の跡継ぎになるのです。その伯爵がまた人のきらわれものなのです。いったいどうなるのでしょう・・・  A Little Princess F.H.Burnett (1905)
A Little Princess F.H.Burnett (1905)こういうストーリーこそ鉄板でしょう。子供時代に浸れた人は幸せです。英書慣れの時期に文句なくおもしろい。  好きだった風 風だった君 みずしま志穂 (1983)
好きだった風 風だった君 みずしま志穂 (1983)主人公、麻野朔美(さくみ)14才、中学3年生。受験生である。父親は公立病院の医者で母親は美人、ひさ子という幼なじみのガールフレンドがいて・・・という何一つ問題ない家庭だが、ゆれ動く朔美の心は複雑である。担任に反抗して白紙の答案を出したり、理由なく早退してみたり・・・そんなある日・・・  第九軍団のワシ ローズマリ・サトクリフ作 猪熊葉子訳 (1954→1972)
第九軍団のワシ ローズマリ・サトクリフ作 猪熊葉子訳 (1954→1972)若きローマの百人隊長マーカスの父は、かつての第九軍団の副司令官だったがその軍団は出征したままただの一名も戻らない不思議な行方知れずになっていた。マーカスは、氏族の反乱を見事防ぐが、自身もけがをして退役する。人生につまずいたマーカスはやり残した父の軍団探しに敵地深く潜入していく・・・
  読書通信「アトレーユ」 38号 読書通信「アトレーユ」 38号 大きな木の下で グレイトン・ベス作 犬飼千澄訳 (1882→1984)
大きな木の下で グレイトン・ベス作 犬飼千澄訳 (1882→1984)アフリカでまだ天然痘(てんねんとう)がはやっていたころ、語り手、モモのところに赤ん坊を連れた旅人が来る。旅人達は夜中この赤ん坊を残して消えていく。気が付くとこの子は天然痘にかかっていた・・・モモの母親ハワウはある決意をした・・・  ハッピーバースデー さとう まきこ (1882)
ハッピーバースデー さとう まきこ (1882)主人公ユカリは六年生。チビで運動神経まるでゼロ。無口で引っ込み思案。一方、ヤーヤンは背が高く、運動なら何でもござれ。いつも教室の話題の中心。ところがこの二人が誕生日が同じ!そして、ユカリの誕生会がヤーヤンの誕生会に台無しにされる・・・  日本のすがた 矢野恒太郎記念会編集 (1988)
日本のすがた 矢野恒太郎記念会編集 (1988)諸君、受験の学年になったらぜひ一冊そろえましょう。『国勢図絵(こくせいずえ)』という資料集の小中学生版です。ひまな時にながめてください。ながめればながめるほどおもしろくなってきます。おもしろいと思ったところから社会科は身近になります。  NHKラジオ講座 『基礎英語』/『続基礎英語』/『上級基礎英語』 4月号 (1882)
NHKラジオ講座 『基礎英語』/『続基礎英語』/『上級基礎英語』 4月号 (1882)NHKのラジオ講座はどれも大変よい番組です。始めるチャンスは何と言っても今です。中1だけでなく、中2は「続基礎英語」を、中3は「上級基礎英語」をどうですか?
  読書通信「アトレーユ」 39号 読書通信「アトレーユ」 39号 冒険者たちーガンバと十五ひきの仲間 斉藤敦夫 (1972)
冒険者たちーガンバと十五ひきの仲間 斉藤敦夫 (1972)街ネズミのガンバがふとしたさそいからおそろしいイタチが支配する夢見が島のネズミたちを助けに仲間15匹と冒険に出る。島に残っているネズミはひょっとすると8ひきだけかも・・・イタチのリーダー、ノロイの知恵とたたかうガンバたちの勇気と冒険には感動しますよ。  ロビンソン・クルーソー ダニエル・デフォー作 坂井晴彦訳 (1719→?)
ロビンソン・クルーソー ダニエル・デフォー作 坂井晴彦訳 (1719→?)諸君はみんなこの人の話はしっているでしょうが、舞台となった無人島が南アフリカのベネズエラを流れる、オリノコ川の河口にあったということになっているのを知らないでしょう?おもしろいのはクルーソーが家を造り、やぎを飼い、麦や米を収穫するまでじゃないかなー?  技術の歴史 クルップ/鉄鋼 井野川潔 (1987)
技術の歴史 クルップ/鉄鋼 井野川潔 (1987)1826年、ドイツのエッセンという町で、14才の少年アルフレッド・クルップが父の鉄工所を引き継いだ。それから75年にわたる鉄鋼に捧げたクルップの生涯の伝記です。鋼の話は難しいのですが、勉強になりますよ。  世界国勢図絵(1988~89年版) 矢野恒太郎記念会編集 (1987)
世界国勢図絵(1988~89年版) 矢野恒太郎記念会編集 (1987)この本は前回紹介の『日本のすがた1988』の大人向けの世界版です。追って紹介する『日本国勢図絵1988』でカバーしきれない部分を2年に1回の発行で補っています。例えばNics(ニックス)の説明はこの本が分担しています。社会科大好き少年少女に勧めます。
  読書通信「アトレーユ」 40号 読書通信「アトレーユ」 40号 小公女 バーネット作 吉田勝江訳 (1905→1954)
小公女 バーネット作 吉田勝江訳 (1905→1954)『小公子』と同じ作者のお話です。7才のセーラーがインドの父のもとからイギリスの全寮制女学校に入る。初めはちやほやされるが、父がなくなると突然女中がわりのひどい扱いをうける。つらい日々の中で、仲よくなった隣の家の人々が・・・  オオカミに冬なし クルト・リュートゲン作 中野重治訳 (1955→1964)
オオカミに冬なし クルト・リュートゲン作 中野重治訳 (1955→1964)1893年、北極海バロー岬沖にとじ込められた捕鯨船7隻の275人の命を救うために政府カッター「牝ぐま号」が出動を命じられる。自船も氷に閉じこめられ動けなくなる。が、航海士ジャーヴィスと船医マッカレンがただ二人で命をかけてアラスカ大陸を横断して捕鯨船を救出する決意を固める・・・  技術の歴史 アークライト/紡績機 井野川潔 (1984)
技術の歴史 アークライト/紡績機 井野川潔 (1984)歴史の教科書では、「1768年、アークライト、水力紡績機を発明」とあるだけなのですが、アークライトは何ととこやさんだったのです。とこやさんがどうして歴史に残る発明をし、最後には貴族にまでなったか?  アラスカ物語 新田次郎 (1974)
アラスカ物語 新田次郎 (1974)2と同じ1893年、米国沿岸警備船「ベアー号」はアラスカ北部ポイントバロー沖の北極海でとじ込められる。キャビンボーイ、フランク安田はベアー号救出のため交易所のあえるポイントバローへ決死の一人旅をする。アラスカ・エスキモーのモーゼと後に言われる明治時代の日本安田恭輔の感動の伝記。
  読書通信「アトレーユ」 41号 読書通信「アトレーユ」 41号 生物の消えた島 田川日出夫 文 松岡達英 絵 (1987)
生物の消えた島 田川日出夫 文 松岡達英 絵 (1987)今からおよそ百年前、1883年8月27日、今のインドネシアのクラカタウ島が大噴火をし、爆発音は2000キロはなれたオーストラリアやタイまで聞こえ、ふきあげた火山灰が落ちてくるのに10年もかかった。もちろん島はその4分の3がふきとん!島のその後の100年の生物の変化にせまる。  続 インガルス一家の物語
続 インガルス一家の物語ローラ・インガルス・ワイルダー作 鈴木哲子・谷口由美子訳 (1940~71→1955~83)
6 長い冬 7 大草原の小さな町 8 この楽しき日々 9 はじめの4年間 付 我が家への道 ローラ一家が小さな払い下げ農地に落ち着き、学校に行き、やがてローラは教師になり、アルマンゾと結婚し、農民として大地とたたかう・・・  技術の歴史 ワット/蒸気機関 井野川潔 (1984)
技術の歴史 ワット/蒸気機関 井野川潔 (1984)当時イギリスでは、開発が進んだ炭坑からわき出す水が炭坑を閉山に追い込んでいた。サヴァリーやニューコメンの蒸気機関が発明されたのだが、能力的に追いつかない。そこで注目されたのが、ワットの蒸気機関!  天平の甍(いらか) 井上靖 (1958)
天平の甍(いらか) 井上靖 (1958)奈良時代。第九次遣唐使の留学僧。普照(フショウ)と栄叡(ヨウエイ)は当時の日本に戒律(僧の規律)をきちんと広める師を唐から招く訳を受け持つ。招きに応じた鑑真(当時55才)は、数次にわたり渡日を試み、難破し、捕縛され、盲てまでして11年かけて約束をはたす。
  読書通信「アトレーユ」 42号 読書通信「アトレーユ」 42号 おじいさんのランプ 新美南吉 ( ? )
おじいさんのランプ 新美南吉 ( ? )以前紹介した「ごんぎつね」の姉妹編です。昔、私たちの祖先が、生きて、苦しいことがあったり、楽しいことがあったりしただろう有様を、なつかしくなつかしく語りかけてきます。なぜおじいさんのランプか?題から何を想像しますか?  小町算と布ぬすっと算――わらべうたと物語でつづるたのしい算数
小町算と布ぬすっと算――わらべうたと物語でつづるたのしい算数山崎直美 (1988) 有名な「鶴亀算」は西暦3世紀の中国の数学書の中では「きじ・うさぎ算」だったのが、日本に伝えられるとめでたい鶴と亀の問題に変わり、「鶴亀算」と呼ばれるようになったんだって!  技術の歴史 スチブンソン/汽車 井野川潔 (1985)
技術の歴史 スチブンソン/汽車 井野川潔 (1985)スチブンソンは14歳のときニューコメン機関の火夫見習いとなり、このエンジンのことなら何でも知った若者となるが、18のときワットのエンジンを知りたい一心で字を覚える。やがて数奇な人生を送るトレビィシックの高圧エンジンの助けを借り、ロコモーション号、ロケット号の発明へと進む。  敦煌(とんこう) 井上靖 (1959)
敦煌(とんこう) 井上靖 (1959)ときは1026年、中国は北宋のころ、趙行徳(チョウギョウトク)はふとした奇縁で西域・西夏国の文字に興味を持ち、西夏の都に行こうとして捕えられ、西夏軍の兵士となる。偶然命を救ったウイグルの王族の王女とのロマンス、行徳が生死を預けた隊長、朱王礼の西夏への反逆・・・
  読書通信「アトレーユ」 43号 読書通信「アトレーユ」 43号 岩宿(いわじゅく)遺跡のなぞ たかしよいち (1976)
岩宿(いわじゅく)遺跡のなぞ たかしよいち (1976)考古学者が、だれ一人見向きもしなかった関東ローム層の赤土から旧石器を発見した相沢さんの話は歴史の教科書にも出ています。ところで、学者たちがなぜそう錯覚したかのわけを今回私は初めて知りました。相沢さんの研究者魂(たましい)の話もすごい。  ビルマの竪琴(たてごと) 竹山道雄 (1948)
ビルマの竪琴(たてごと) 竹山道雄 (1948)「はにゅうの宿」という歌知ってる?元の名前は「 Home Sweet Home 」です。あなた方のおじいさん、おばあさんの若いころ日本はビルマでイギリスと戦っていたことはどう?竪琴の名手、水島上等兵は?水島が味方を救いに行って消息不明になったことは?水島そっくりのビルマ僧が今もひょっとするとビルマの原野を歩いていることは?  技術の歴史 アインシュタイン/相対性理論 井野川潔 (1984)
技術の歴史 アインシュタイン/相対性理論 井野川潔 (1984)アインシュタインと技術との関わりは彼の特殊相対性理論の「物質はエネルギーにすっかり変えられる」という予言が原爆に結びついたからです。  君たちの生きる社会 伊藤光晴 (1978)
君たちの生きる社会 伊藤光晴 (1978)今から10年前に出版された本です。「少し古い所があるかな?」と思いながら読みましたが、とんでもない。冒頭の19世紀後半にはアルミニウムという新しい銀は当時「金」と同じ値段だったという話から、もうすでに「へーそうなの!」と私はうなりながら読みましたよ。
  読書通信「アトレーユ」 44号 読書通信「アトレーユ」 44号 新版 野尻湖のぞう 井尻正二 (1976)
新版 野尻湖のぞう 井尻正二 (1976)長野県の北のはし野尻湖の底から1948年、ナウマン像の化石が発見された。日本にいた像のすがたを求めて、野尻湖の水が干上がる冬に集団発掘を続け、ナウマン像のすがたが次第にはっきりしてくる。ナウマン象ははたしてどんな像だったのか?どう発掘したか?  コンチキ号漂流記 ハイエルダール作 神宮輝夫訳 (1948→1976)
コンチキ号漂流記 ハイエルダール作 神宮輝夫訳 (1948→1976)コンチキとは太陽の子チキという意味。南米ペルーの伝説と遠く南太平洋ポリネシアの伝説が不思議に一致する。著者はこのことを確かめるためにいかだで太平洋を航海しようと計画する。いかだは海面上0メートルの乗り物。エンジンはもちろんなし。風まかせ波まかせの冒険は?  ファーブルの昆虫記 アンリ・ファーブル作 山田吉彦訳 (1879~1910→1953)
ファーブルの昆虫記 アンリ・ファーブル作 山田吉彦訳 (1879~1910→1953)一部の中1の国語教科書にのっている「フシダカバチの秘密」はもちろん、ふんころがしのタマオシコガネが西洋なしそっくりの玉を作る話。セミの子は食べられるかと実験した話・・・など、「難しい」けれどどの話もその味わいはすばらしい。ゆっくり、ゆっくり読むといいね。  大仏建立物語 神戸淳吉 (1972→1988)
大仏建立物語 神戸淳吉 (1972→1988)奈良の大仏は知っているよね?奈良時代に建てられたのだけれど、頭は二度、胴は一度、戦争のため焼けてとけたり、こわれたりしています。明治時代には古い文化が見捨てられ、何と大仏を大砲でつぶす計画まで立てられたこともあるそうです。興味津々。
  読書通信「アトレーユ」 45号 読書通信「アトレーユ」 45号 ピーターパンとウエンディ J・M・バリ作 石井桃子訳 (1911→1972)
ピーターパンとウエンディ J・M・バリ作 石井桃子訳 (1911→1972)ウエンディ、ジョン、マイケルの3人の姉弟は、生まれた日に家出をしたピーターパンと、空を飛んでネバーランドに行く。どうしてかって?行きたかったからさ。ネバーランドでは、海賊フックの一味がいた。どうしてかって?いないと話にならないからさ。いいから読んでみな!  ひろがるさばく 赤城昭夫 文 浅野邦夫 絵 (1979)
ひろがるさばく 赤城昭夫 文 浅野邦夫 絵 (1979)今のサハラ砂漠のまんなかの山の谷間のかべに3000年前に書かれたカバの絵がある。カバは水辺の動物だ。するとサハラは5000年前は水が流れていた?・・・同じころメソポタミアではコムギがとれていたが、取れ高をとして水を余分に引いたところ砂漠化が進んだ!  ファーブル 昆虫と暮らして アンリ・ファーブル作 林達夫編訳 (1879→1910)
ファーブル 昆虫と暮らして アンリ・ファーブル作 林達夫編訳 (1879→1910)この本を読んでいくと君たちはきっとファーブルが大好きになりますよ。「知る」ことが並はずれて好きで、貧しさに耐え忍んで研究し続け、56才で『昆虫記』を書き始め、90才で『昆虫記』決定版に序文を書くまでのファーブル伝です。『昆虫記』と一緒に読もう。  緑の冒険――砂漠にマングローブを育てる 向後元彦 (1988)
緑の冒険――砂漠にマングローブを育てる 向後元彦 (1988)これは痛快な本です。マングローブとは干潮には陸地になり、満潮になれば海になる潮間帯で育つ樹種の総称です。つまり塩分に強いのです。中近東の砂漠に絶好の「緑のもと」だとひらめいた向後さんの人生をかけた冒険物語。2とあわせて読むといい!
(c) 2004-2014 必ず役に立つ体験記
|