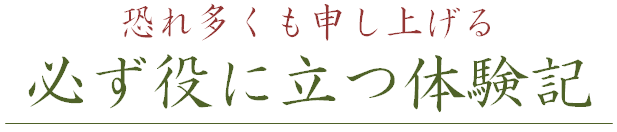|
鉄板の面白さ!「児童書300選」
〈その4〉
 読書通信「アトレーユ」 46号 読書通信「アトレーユ」 46号 クマのプーさん A・A・ミルン作 石井桃子訳 (1911→1972)
クマのプーさん A・A・ミルン作 石井桃子訳 (1911→1972)「プーさん」とは作者ミルンの息子クリストファー・ロビンのぬいぐるみのクマなのですが、お父さんがクリストファーにお話してあげるときは、生きて動き始めるのです。コブタ、ロバのイーヨー、カンガルーのカンガ、ウサギ、フクロ、ゾゾなど、かわいくて、うれしくなってしまう動物たちがいっぱい!  ダイコンを育てる 須之部淑男(よしお)文 村田道紀 絵 (1979)
ダイコンを育てる 須之部淑男(よしお)文 村田道紀 絵 (1979)表紙の絵は桜島ダイコンです。最高記録は40㎏だそうです。11ページの絵は守口ダイコンです。長いものは175㎝にもなるそうです。同じダイコンでこれほど違うのにはビックリですね。このダイコンという植物のふるさとは何とヨーロッパの地中海なのだそうですよ!  君たちはどう生きるか 吉野源三郎 (1977)
君たちはどう生きるか 吉野源三郎 (1977)主人公本田純一は中学2年生。あだ名はコペル君。友達の北見君がいいがかりをつけられて上級生になぐられる。団結を誓ったコペル君たちの中で、助ける仲間にコペル君だけがこわくてはいりそこなった。コペル君は罪の意識で寝込んでしまう・・・  流れる星は生きている 藤原てい (1965)
流れる星は生きている 藤原てい (1965)昭和20年8月9日、満州・新京からの移動命令に始まる。六歳と三歳の男の子と生まれて一ヶ月の女の子を連れた藤原ていさんの引き揚げ体験記。個人的なことですが、私の母も引き揚げてきたことを思い、語ろうとしない母の苦労を私はしのびました。
  読書通信「アトレーユ」 47号 読書通信「アトレーユ」 47号 ペットねずみ大さわぎ フィリッパ・ピアス作 高杉一郎訳 (1973→1984)
ペットねずみ大さわぎ フィリッパ・ピアス作 高杉一郎訳 (1973→1984)シド・パーカーはともだちからペットのねずみをもらう。家にかくしていたが、おかあさんにみつかった。あかあさんは動物を家で飼うのは大嫌い。次の日おとうさんが返しにいくと、断られる。広告を出し、ほしい人が取りにくるが、ねずみはまたもどってくる・・・  クリスマス・キャロル チャールズ・ディケンズ作 村上英太郎訳 (1843→1950)
クリスマス・キャロル チャールズ・ディケンズ作 村上英太郎訳 (1843→1950)スクルージー老人は金持ちだが、けちで孤独(こどく)で、クリスマスを祝うなどもってのほかと長年思ってきた。クリスマスイブの晩、自分の過去を見せるゆうれいの訪問を受け、次の晩は、現在を見せるゆうれい、最後は自分の未来を見せるゆうれいが来る。はたして彼の未来は・・・?  太平洋漂流実験50日 斉藤実 (1987)
太平洋漂流実験50日 斉藤実 (1987)「海で遭難し、漂流したときに、真水がなくて死に至ることが極めて多い。だが、もし海水が飲めたなら・・・」という実験に命をかけてきた斉藤さんの記録。何度かの実験の末、マリアナ諸島から沖縄に向けて決死の漂流を開始する。。だが、そこに台風が襲来する・・・  ボクの学校は山と川 矢口高雄 (1987)
ボクの学校は山と川 矢口高雄 (1987)「釣りキチ三平」の著者の少年時代の話。釣り糸をヤママユガの毛虫から自分で作る話や、底なし沼に落ちかかる話。ツチノコを見た話など、同じ日本の話とは思えないほどの、文字通り「山と川」いっぱいの厳しいが自由な少年時代!
  読書通信「アトレーユ」 48号 読書通信「アトレーユ」 48号 人間・野口英世 秋元寿恵夫 (1983)
人間・野口英世 秋元寿恵夫 (1983)野口英世という人をしっていますか?え、知っている?「えらい人」だって?ではどう「えらかった」の?わすれた?じゃーもう一度この本を読むといいよ!細菌学者野口にとってウイルスを予想することが困難であったことを知ることはつらいよ・・・  中国の歴史(中公コミックス)全12巻 陳瞬臣 手塚治虫監修 (1986~1987)
中国の歴史(中公コミックス)全12巻 陳瞬臣 手塚治虫監修 (1986~1987)例えば、25号で紹介た司馬遼太郎の「項羽と劉邦」は1103ページあったのですが、同じ話がこの漫画シリーズでは112ペ-ジです。諸君ならおそらく一冊を30分以内で読めます。だから一気に読むことをおすすめします。おもしろいよ!中国の歴史の通になれるよ!  ボクの先生は山と川 矢口高雄 (1988)
ボクの先生は山と川 矢口高雄 (1988)前作に続いて山村の生活をつづっています。表紙の絵は「山彦」つまり、オーイとさけぶとオーイと答えるこだまを採ろうとしている絵です。「エッ何いってんだい、笑うぜ」と言うかもしれませんが、読むと反対に泣けてきます。  生きている石器時代 ニューギニア高地人 本田勝一 (1976)
生きている石器時代 ニューギニア高地人 本田勝一 (1976)昭和39年一月、朝日新聞の本田記者たちはニューギニア高地のウギンバ部落で、モニ族とダニ族の中で暮らし始めた。25年前の話である。彼らは裸とはちょっと違う服装で、イモを作って生活している。歴史風にいうと無土器文明である。まあ、写真を見たまえ!
  読書通信「アトレーユ」 49号 読書通信「アトレーユ」 49号 記号・単位の秘密 押田勇雄 監修 川崎てつお 他 漫画 (1981)
記号・単位の秘密 押田勇雄 監修 川崎てつお 他 漫画 (1981)この漫画には、君たちがきらいな%や長さや面積の単位のできかたや見分け方がのっています。すべてがわかるわけはもちろんありませんが、「なるほどなー」と思うこともきっと多いよ。  オウムガイの謎(なぞ) 小畠郁生・加藤秀 (1987)
オウムガイの謎(なぞ) 小畠郁生・加藤秀 (1987)オウムガイとは何でしょう。貝の仲間ではないのだそうです。生きている化石と言われ、タコやイカの親類で、今から5億年前に3500種類にも分かれて全盛をほこっていたが、現在はわずか3種類がひっそりと生きているだけ。その水族館での熱心な飼育記録。  ヘンリー・シュガーのわくわくする話 ロアルド・ダール (1977→1979)
ヘンリー・シュガーのわくわくする話 ロアルド・ダール (1977→1979)ヘンリー・シュガーという大金持ちが「目を使わずにものを見る」というヨガの行者の術の秘密を手にいれる。この術は大変な集中力が必要で、ヘンリー・シュガーは3年と3ヶ月かかってようやく精神を4秒集中することで目を使わずにものを見ることができるようになる!  運命の騎士 ローズマリ・サトクリフ作 猪熊葉子訳 (1960→1970)
運命の騎士 ローズマリ・サトクリフ作 猪熊葉子訳 (1960→1970)サトクリフの本もこれで紹介5冊目。舞台はイギリス。名前はランダル。父は戦死。母はランダルが生まれるとすぐに死んだ。領主の犬番の所で一人で育つ。その彼がふとした偶然でディーンの騎士エベラーード・ダグイヨンに仕え、表題の通り「運命」の糸が導くままやがて・・・
  読書通信「アトレーユ」 50号 読書通信「アトレーユ」 50号 アメリカの歴史(中公コミックス)全12巻 猿谷要 手塚治虫 監修 (1987~1988)
アメリカの歴史(中公コミックス)全12巻 猿谷要 手塚治虫 監修 (1987~1988)アメリカ合衆国は歴史が浅い国だとよく言われますが、こうして漫画にしてみると、それなりにいろいろなことがあったのですね。「大陸横断鉄道」「鉄鋼王カーネギー」「自動車王フォード」の話が知らないことだらけで私には特におもしろかったですよ!  人類の長い旅 ビッグ・バンからあなたまで
人類の長い旅 ビッグ・バンからあなたまでK・マーシャル著 藤田千枝訳 (1980~1983) ビッグ・バンは宇宙の始まりの〈大爆発〉のことです。生命とはまだ言えない「前細胞」から「最初の細胞」が現れるところや、ヒトの先祖がどういう風に出現して来たかをわかりやすく説明しています。14号で紹介した「せいめいのれきし」と合わせて読むといい!  原始人の技術にいどむ 岩城正夫 (1980)
原始人の技術にいどむ 岩城正夫 (1980)産業革命のもとであるジェニー紡績機についての教科書の間違いを岩城さんは発見した。誰も疑わないことを自分で糸を紡ぐところから初めてみたのである。近くの遺跡から出た石器も教科書に書いてある石器とは性質が違う。なぜなのだろう・・・次の疑問である。  スズメバチの死闘-―ぼくの動物記 川島民親 (1988)
スズメバチの死闘-―ぼくの動物記 川島民親 (1988)筆者たちは子どものころ、コガタスズメバチやキイロスズメバチを十年バチと呼んでいた。さされて十年たてば死ぬのだそうな。ましてオオスズメバチは百年バチそのものだった。著者と百年バチの、はたき落としたり、刺されたりの交流が、輝く思い出の中で続いていく・・・
  読書通信「アトレーユ」 51号 読書通信「アトレーユ」 51号 世界の歴史(中公コミックス)全15巻 手塚治虫 監修 (1983~1985)
世界の歴史(中公コミックス)全15巻 手塚治虫 監修 (1983~1985)『日本の歴史』『中国の歴史』『アメリカの歴史』と続いて、いよいよ世界の歴史です。「インカ帝国の悲劇」「ルネッサンス」「インド独立の戦い」など、教科書の説明ではわかりにくい話が漫画にしたことで、なるほどとうなづけるのだから不思議ですよ!  きみのそばにダニがいる 青木淳一 (1989)
きみのそばにダニがいる 青木淳一 (1989)ダニといってもたたみやじゅうたんにいて君たちの血を吸う種類はここでは登場しません。ダニは日本中のあらゆる場所にいて、森の中では中学1年生の片足ほどの面積に何と725匹もいるそうです。気持ち悪い?読んでみるとけっこう親しみがわきますよ!  星は生きている 星の誕生からブラックホールまで 野本陽代 (1987)
星は生きている 星の誕生からブラックホールまで 野本陽代 (1987)実は太陽には兄弟星がある!ということを知ってましたか? この本は、太陽のような恒星ができ、気の遠くなるほど長い年月を経て、地球などを呑みこんで赤い大きな星(赤色巨星)となり、やがて死んで行くまでをわかりやすく説明してくれます。  縄文生活の再現 楠本政助 (1988)
縄文生活の再現 楠本政助 (1988)以前3号で紹介した『縄文人の千枝にいどむ』という作品の著者、楠本さんの大人向け文庫版です。鹿の角から作る釣り針やもりの話はここでも興味尽きないものがありますが、夏休みに子どもたちと「竪穴住居」で生活してみる話もわくわくしますよ。
  読書通信「アトレーユ」 52号 読書通信「アトレーユ」 52号 NHKおもしろ漢字ミニ辞典 全12巻 竹田晃 監修 加藤晃 まんが ( ? )
NHKおもしろ漢字ミニ辞典 全12巻 竹田晃 監修 加藤晃 まんが ( ? )12巻の中に24の漢字のグループの解説があります。漢字は形をまねた字、象形文字からできたことを改めて一つ一つ教えてくれます。「美」が「大きな羊」からきている字だとか、「亥」が「豚の骨」だとか、なぜ「空」が「あなかんむり」かとか・・・  ヒルズ・エンド アイバン・サウスオール作 小野章訳 (1962→1976)
ヒルズ・エンド アイバン・サウスオール作 小野章訳 (1962→1976)オーストラリアの田舎の村の少年たちの話。村のヒトが年に一度の町へのピクニックに全員出かける日に13才のポールとアドリアンはこともあろうにけんかを始め、ピクニックには行けなくなる。その日午後村は大嵐になり、洪水に流されてしまう!残ったのは子どもたちだけ・・・  ゴリラ探検記 河合雅雄 (1977)
ゴリラ探検記 河合雅雄 (1977)1959年、マウンテンゴリラの研究がまだ始まったばかりのころのサル学者の探検記。ゴリラの正体にせまろうと近づくあまり、襲われるところはこわい!当時の推定生息数3000~5000頭とあるますが、先日のテレビ番組によると今では350頭だそうですよ!  大地の子エイラ-始原への旅だち 第1部
大地の子エイラ-始原への旅だち 第1部ジーン・アウル作 中村妙子訳 (1980→1983) 紀元前3万年ごろ、今の黒海の北部が舞台。クロマニヨン人の5才の娘エイラが地震で一族を失い、ネアンデルタール人の部族の薬師イザに拾われる。一族のまじない師クレブの保護を受け、醜いよそ者の扱いながら、部族にとけ込んでいく。しかし、新しい族長ブラウドは・・・
  読書通信「アトレーユ」 53号 読書通信「アトレーユ」 53号 NHKおもしろ漢字ミニ辞典第2集 全12巻 竹田晃 監修 加藤晃 まんが ( ? )
NHKおもしろ漢字ミニ辞典第2集 全12巻 竹田晃 監修 加藤晃 まんが ( ? )第1巻と同じく、12巻の中に24の漢字のグループの解説があります。どの巻にも表紙裏にかいせつがあり、それがまた、いい。21巻に倉頡(そうけつ)さんという目が四つある、漢字を考え出した人が出てきます。もちろん倉頡は伝説の人です。では漢字は誰が・・・  八十日間世界一周 ジュール・ヴェルヌ作 田辺貞之助訳 (1873→1976)
八十日間世界一周 ジュール・ヴェルヌ作 田辺貞之助訳 (1873→1976)1873年とは明治6年です。主人公フィリアス・フォッグが当時の最新の交通手段を駆使してスエズ、インド、中国、日本、アメリカ、そしてイギリスへと80日で一週するかけをする。線路が未完成、客船に乗りそこない、インディアンと戦い・・・とやっとニューヨークに着くが、45分の差で最後の船は・・・  エヴェレストをめさじて ジョン・ハント作 松方三郎訳 (1954→1954)
エヴェレストをめさじて ジョン・ハント作 松方三郎訳 (1954→1954)「そこに山があるから」エヴェレストに登ったヒラリーとテンジンの隊の登山隊長の記録です。まあ、諸君、27ページの全隊員の顔写真をごらんよ!みんな、ほれぼれする顔してるぜ!こういう顔をいい顔っていうんだぜ。登ったのは二人だけど、登れたのはこういうわけだったのさ。  チンパンジーを追ってル 伊谷純一郎 (1970)
チンパンジーを追ってル 伊谷純一郎 (1970)52号のゴリラの話と一対になった好著です。アフリカはタンザニアのサバンナ・ウッドランドにチンパンジーを追う苦労が身近に迫ります。この本では、ライオンはスワヒリ語でシンバとあえて記述するごとく、伊谷さんアフリカになりきっています。諸君もンドロボーをさけながらソコムツにせまろう!
  読書通信「アトレーユ」 54号 読書通信「アトレーユ」 54号 お金と社会-政府と民衆の歴史 板倉聖宣 (1982)
お金と社会-政府と民衆の歴史 板倉聖宣 (1982)日本で作られた最初のお金は和同開珎ですが、人々はこのお金を喜んで使ったでしょうか。にせ金を作る人は知らなかったのでしょうか。江戸時代でも通用したのでしょうか。知らないことだらけ!  科学的とはどういうことか 板倉聖宣 (1977)
科学的とはどういうことか 板倉聖宣 (1977)小学校の理科での実験で、なぜか水の沸騰点が100℃にならず、97℃で沸騰してしまう例が続出。原因はどこにあるか、と調べていくと・・・話はやがてアルコール温度計の中に入っている液ははたして、アルコールか?というところに進んでいく。  原子とつきあう本 板倉聖宣 (1985)
原子とつきあう本 板倉聖宣 (1985)中学2年生や中学3年生は原子とか分子とかイオンとかの勉強をしていますね。現在発見され、確認されている原子は103。原子のことなら発見の時期、性質、記号の由来、覚え方から何と値段まで、それこそ何でものっています。このページの下の文はなあ~んだ?  歴史の見方考え方 板倉聖宣 (1986)
歴史の見方考え方 板倉聖宣 (1986)江戸時代の農民は何を食べていたのでしょうか?米、麦、雑穀、いもなど・・・の何だったのでしょう。貧しくて米など食べられなかった?江戸時代の人口はどのくらいだったのでしょう。知ってそうで知らない問題を追及していくと見えなかった歴史が見える。
  読書通信「アトレーユ」 55号 読書通信「アトレーユ」 55号 だれも知らない小さな国 コロボックル物語 1 佐藤さとる (1959)
だれも知らない小さな国 コロボックル物語 1 佐藤さとる (1959)コロボックルという伝説の小人を知っていますか。表紙の絵はどこかで見たことあるでしょう。主人公が小学3年のころふとみつけた秘密の場所。そこには実はコロボックルが生存していたのです。  太平洋ひとりぼっち 堀江謙一 (1962)
太平洋ひとりぼっち 堀江謙一 (1962)今世界一小さなヨットで太平洋横断をしている真っ最中の堀江さんが日本人で初めての単独太平洋横断を94日かけて決行した記録。先輩に「今夜、出かけまんねん」と電話し、西宮から出航。パスポートがないから密航である。太平洋をはるかサンフランシスコまで!  翼よあれがパリの灯(ひ)だ チャールズ・A・リンドバーグ作 佐藤亮一訳 (1977)
翼よあれがパリの灯(ひ)だ チャールズ・A・リンドバーグ作 佐藤亮一訳 (1977)世界で初めて飛行機で大西洋を無着陸横断した記録。リンドバーグは出発のときすでに前日から23時間眠っていない。パリに着くまで33時間30分眠らずに飛行機を操縦する。燃料の積み過ぎでやっと飛び立つには飛び立ったが、前方には嵐と睡魔が・・・  よみがえれ黄金(グガニー)の島 小山重郎 (1984)
よみがえれ黄金(グガニー)の島 小山重郎 (1984)熱帯・亜熱帯を原産とするミカンコミバエは台湾経由ですでに1919年には沖縄に侵入していた。以後沖縄のミカンは、絶滅宣言が出される1982年まで本土に出荷できなかった。沖縄からミカンの害虫ミカンコミバエを絶滅させるまでの学者と現場行政官の感動的記録。
  読書通信「アトレーユ」 56号 読書通信「アトレーユ」 56号 豆つぶほどの小さな犬 コロボックル物語 2 佐藤さとる (1962)
豆つぶほどの小さな犬 コロボックル物語 2 佐藤さとる (1962)55号で紹介した『誰も知らない小さな国』の続編です。今度の主人公はせいたかさんではなくて、コロボックルのクリノヒコたち。先祖が飼っていたマメイヌが生きていくかもしれない!それもそう遠くなく・・・  火の玉の科学 大槻義彦 (1989)
火の玉の科学 大槻義彦 (1989)表紙を見て下さい。火の玉です。お話の中だけでなくこの世に存在するのですね。火の玉の目撃例をたんねんに調べていくと季節・場所が「かみなり」発生の例とほぼ重なるそうです。物理学者である著者は火の玉の正体を確かめ実験室でも作り出すのです。  磁石の魅力 板倉聖宣 (1980)
磁石の魅力 板倉聖宣 (1980)この本では磁石の「磁」という字の考察から始まります。磁はもとは慈(いつくしむ)と書いた。慈石にはおっぱいが二つあり、そのおっぱいで鉄をわが子のようにひきよせる(=いつくしむ)からだそうです。後半は天然磁石を探して、意外な所にあった話です。  ご冗談でしょう、ファインマンさん Ⅰ・Ⅱ R.P.ファインマン作 大貫昌子訳 (1985)
ご冗談でしょう、ファインマンさん Ⅰ・Ⅱ R.P.ファインマン作 大貫昌子訳 (1985)量子電磁力学のくりこみ理論(?)でノーベル賞をとた著者のユニークな生き方にはうなります。初めの章の題が「考えるだけでラジオを直す少年」ときます。青年時代、金庫破りの名人と言われたり、ボンゴをたたいて本職一歩手前になったり、絵を描けば高く売れたり!
  読書通信「アトレーユ」 57号 読書通信「アトレーユ」 57号 ある池のものがたり 三芳梯吉(ていきち) (1986)
ある池のものがたり 三芳梯吉(ていきち) (1986)今から100年ほど以前のこと、新潟市のはずれで、教会のわきに井戸を掘ったところが水がわき出して池になった。以来60年、洪水や火事や戦争やらの中でこの池は市民のいこいの場となったが・・・  星からおちた小さな人・ふしぎな目をした男の子 コロボックル物語 3・4
星からおちた小さな人・ふしぎな目をした男の子 コロボックル物語 3・4佐藤さとる (1980) 55・56号で紹介した誰も知らない小さな国シリーズの続編です。「星から落ちた小さな人」では、コロボックルは自分たちの空飛ぶ機械を作り出す。ところが、試験飛行中に事故が起きる・・・「ふしぎな目をした男の子」では、あのすばやいコロボックルのことが目に見える子がいた!  日本の都道府県 板倉聖宣 (1987)
日本の都道府県 板倉聖宣 (1987)あなたは、都道府県の名をどれだけ知っていますか。面積の最も大きいところは?もっともせまいところは?人口の少ないところを3位まで言うと?県庁所在地と都道府県名が同じ名のところはいくつありますか?政令指定都市とはどんな都市ですが?・・・  困ります、ファインマンさん R.P.ファインマン作 大貫昌子訳 (1988)
困ります、ファインマンさん R.P.ファインマン作 大貫昌子訳 (1988)1986年1月28日、スペースシャトル、「チャレンジャー」号が発射直後大爆発した事故を覚えていますか?この事故の「調査委員会」の委員にされたファインマンの面目躍如の活躍と、なぜか知らないが、本当の原因発表がゆがめられていくドキュメントです。これだけでも十分おもしろい。
  読書通信「アトレーユ」 58号 読書通信「アトレーユ」 58号 ジュニア地図帳 こども日本の旅 高木実 構成 花沢真一郎 イラスト (1987)
ジュニア地図帳 こども日本の旅 高木実 構成 花沢真一郎 イラスト (1987)小学生向けの地図帳です。名所や名産や県の旗や県の木、工業地帯の図解、海の水の高さと日本の領土など、どのページもどのページも楽しくおもしろいですよ!世界編や歴史編もあるよ。  海にしずんだ島 幻の瓜生島(うりゅうじま)伝説 加藤知弘 (1987)
海にしずんだ島 幻の瓜生島(うりゅうじま)伝説 加藤知弘 (1987)大分県に別府湾という湾があります。今から400年ほど以前にそこに沖の浜という港があり、あの有名なフランシスコ・ザビエルもこの港からの船に乗ってインドに帰ったのだそうです。ところが、この浜は瓜生島という島にあり、その島は大地震で水没したらしい・・・  最後のひと葉 オー・ヘンリー傑作短編集
最後のひと葉 オー・ヘンリー傑作短編集オー・ヘンリー作 大久保康雄訳 (1906~1910→1989) 中3の英語の教科書に「A Present For You」という課があります。原作はこの本の『賢者の贈り物』なのです。『最後のひと葉』も題を聞いただけで、「あ、知っている」と言う人がいます。話はどれも結末まで何がおこるかわからない意外性に満ちています。  日本国勢図絵(こくせいずえ) 財団法人矢野恒太記念会編 (1989)
日本国勢図絵(こくせいずえ) 財団法人矢野恒太記念会編 (1989)中3社会の授業中にさんざん登場した本です。これを読書として扱うのは難しいです。全部を読むものではないからです。パラパラとページをめくっていって下さい。ときどき「おやっ?」と思うおもしろい統計や地図がありますよ。そう、雨の日の友なのです。
  読書通信「アトレーユ」 59号 読書通信「アトレーユ」 59号 ジュニア地図帳 こども歴史の旅 高木実 構成・文 (1989)
ジュニア地図帳 こども歴史の旅 高木実 構成・文 (1989)小学生向けの歴史地図帳です。世界歴史の地図が変わっています。北極を中心とした世界地図なのです。日本と世界がたがいちがいに説明されているのもおもしろいですよ。中学生でもあきないよ。  小さい牛追い、牛追いの冬 マリー・ハムスン作 石井桃子訳 (1933→1969)
小さい牛追い、牛追いの冬 マリー・ハムスン作 石井桃子訳 (1933→1969)『小さい牛追い』はノルウェーの小学3年と5年の男の子の夏休みの話。初めて山の農場で牛の番をするのです。君たちもしてみたい?牛の番ってけっこう大変なんだってわかるよ。それに、この二人の少年は君たちにそっくりな兄弟げんかをするんでビックリ!  海賊(かいぞく)の島 J・R・タウンゼント作 神宮輝夫訳 (1976)
海賊(かいぞく)の島 J・R・タウンゼント作 神宮輝夫訳 (1976)主人公のあだなはソーセージ・ドッブズ。肉屋のころころちゃん。いじめられっ子。友達はいない。ふと知り合った空想好きの年下の女の子シーラーとボロ机を逆さにしたあわれないかだで下町の川の探索を始める。その探検がとんでもない大事件につながっていく・・・  北極海へ -あめんぼ号マッケンジーを下る- 野田知佑(ともすけ) (1987)
北極海へ -あめんぼ号マッケンジーを下る- 野田知佑(ともすけ) (1987)カナダ北西部を流れ北極海に注ぐ1800㎞のマッケンジー川をカヌーで漕ぎ下る71日の旅!最初に驚くのは黒い煙のようになって群がる蚊(か)の多さ。魚は糸を垂れればすぐ釣れる。川は大きく、寝たり、本読みしながら漕ぎもする。インディアンも出ればエスキモーも出る。
  読書通信「アトレーユ」 60号 読書通信「アトレーユ」 60号 ぼくらの地図旅行 那須正幹 文 西村繁男 絵 (1989)
ぼくらの地図旅行 那須正幹 文 西村繁男 絵 (1989)シンちゃんと安井くんのけんかからシンちゃんとタモちゃんが岬まで地図をたよりに旅行をすることになった・・・知らない土地を地図をたよりに迷いながら岬まで行くと、あるはずの灯台がない!  ようこそおまけの時間に 岡田淳 (1989)
ようこそおまけの時間に 岡田淳 (1989)主人公小6の松本賢。いつもぼんやりしている。四時間目に近くの工場の12時のサイレンが鳴ると夢を見る。夢の中で賢はいばらにとりまかれた状態で教室にすわっている。とげで手すら動かせない。次の日も次の日も見る夢に、賢はカッターナイフを夢に持ち込もうとする。  こちらナースステーション わたしの看護日誌 井部俊子 (1988)
こちらナースステーション わたしの看護日誌 井部俊子 (1988)井部さんは早稲田を落ちて聖路加看護大学に合格したので看護婦になったそうです(へー人生そこで変わったのだ・・・)実習生のときの体験、看護婦になっての日々、やがて婦長になり、大学院に入り直し・・・看護大学の先生になるまでの患者さんや病院の人々を描く感動的な日誌。  マリ16歳、アメリカホームステイ便り 田村真理 (1989)
マリ16歳、アメリカホームステイ便り 田村真理 (1989)高校2年生の著者がアメリカに留学したときの体験記。オハイオ州のデイトンという人口84万人の町。留学先の家庭の間取りの絵が23頁にあるけれど、見ると、「夢と現実」の差がわかります。最初の夕飯はマグドナルドに留学先の一家で食べに行ったというのにも驚きます。
(c) 2004-2014 必ず役に立つ体験記
|